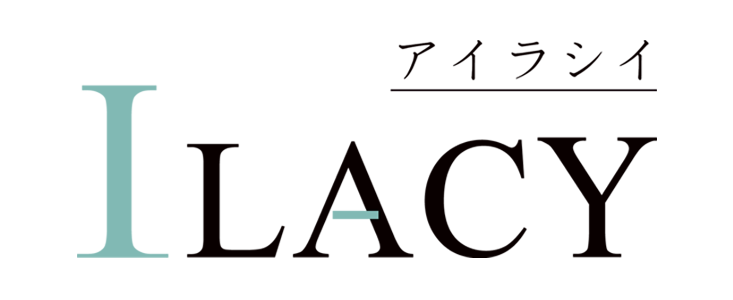【2025年】いま知っておきたい「ワクチン」最新事情―種類・助成・副反応まで徹底解説


東京ミッドタウンクリニック
源河 いくみ(専門分野:感染症内科)
「ワクチンって本当に必要なの?」「どのような状況で何のワクチンの種類を選べばいいの?」「子どもの頃に受けた予防接種。あれから何十年も経って、今さらワクチンなんて...」と迷ったことはないでしょうか。新型コロナウイルスの流行以降、ワクチンに対する関心が高まる一方で、種類や助成、副反応など分かりにくい点も多く、不安や疑問を感じている方も多いでしょう。
ワクチンは感染症予防の切り札であり、正しい知識を持つことで自分や家族の健康を守る大きな力となります。
本記事では、ワクチンの基本情報や大人がいま接種すべきワクチンなどを、感染症内科医の源河いくみ先生が徹底的に解説します。
ワクチンの基本情報
ワクチンの効果とは?
ワクチンは、体にあらかじめ無害化された病原体の情報を届け、免疫を"準備状態"にしておく医療です。
- 感染を防ぐ(予防効果)
- 重症化を防ぐ(合併症・入院・死亡のリスク低減)
- 他人にうつさない(集団免疫の維持・家族を守る)
ワクチンの安全性と主な副反応
日本で承認・使用されているワクチンは厚生労働省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)の厳格な審査を経ており、安全性と有効性が証明されたもののみが使用されています。 ワクチンの主な副反応には軽度なものが多く、次のようなものがあります。
- 注射した部位の痛みや腫れ、赤み
- 発熱
- 筋肉痛
- 倦怠感
- 頭痛
これらの症状は多くの場合、数日以内に自然に軽快します。例えば、帯状疱疹ワクチン(シングリックス®)では、注射部位の痛みや赤み、腫れ、筋肉痛、疲労、頭痛、発熱などの副反応が比較的高い頻度で現れることが知られていますが、ほとんどは3〜7日以内におさまります。
なお、ごくまれに、アナフィラキシーなどの重篤なアレルギー反応が起こることがありますが、こうした重い副反応は接種後15分から30分以内に発症することが多いため、接種後はしばらく医療機関で様子を見ることが推奨されています。
また、ワクチンの種類によっては、まれに心筋炎やギラン・バレー症候群などの重篤な副反応が報告されているものもあります。接種を受ける際は、これまでの接種歴や体調を医師とよく相談し、不安な点があれば事前に説明を受けておくと安心です。
混合ワクチンについて
MRワクチンや5種混合ワクチンなどの混合ワクチンは、複数の感染症に対する成分を一度に接種できるため、通院や接種回数の負担を大きく減らすことができます。これにより、接種スケジュールが簡略化され、打ち忘れや接種率の低下を防ぐ効果が期待できるでしょう。
予防効果については単独ワクチンと同等であることが多く、必要な免疫を効率よく獲得できる点もメリットです。また、副反応についても、単独ワクチンと比べて大きな差はないとされていますが、複数の成分が含まれるため、まれに副反応が重複して現れることがあります。
助成制度について
ワクチンには、公費助成(無料/一部助成あり)がある「定期接種」と、自己負担が基本の「任意接種」があります。
定期接種の対象には、おもに乳児・小児に接種する水痘や麻疹・風疹(MR)ワクチン、日本脳炎、65歳以上に接種する肺炎球菌や帯状疱疹ワクチンがあります。
新型コロナワクチンは定期接種対象(65歳以上など)ですが国の全額の助成が終了し、自己負担額が増加しています。
帯状疱疹ワクチンは2025年4月から定期接種化されましたが、自治体ごとに経過措置対象者への追加支援が異なります。
なお、季節性の流行や地域ごとの感染症の発生状況によって、接種の優先順位や推奨されるワクチンが変わることもあります。自治体によっては特定の年齢層やリスクの高い人を対象に、期間限定で追加接種や助成キャンペーンを行う場合もあるため、最新のお住まいの自治体の情報を確認し、必要に応じて医師と相談しながら接種を検討することが大切です。
大人に勧めるワクチンの概要と特徴

感染症は年齢や環境によってリスクが変化します。
乳児・小児期に必要なもの、加齢とともに必要になるもの、あるいは海外渡航の際に求められるものなど、私たちは生涯にわたり「ワクチン」と付き合っていく必要がありますが、大人が接種した方が良い代表的なワクチンの特徴と最新動向を解説します。
帯状疱疹ワクチン
帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹を防ぐワクチンで、65歳を迎える方などに2025年4月から定期接種化されました。
帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化で発症します。ウイルスは幼少期の水痘(水ぼうそう)感染後に神経節に潜伏し、加齢や免疫力低下により再活性化して神経痛や発疹を引き起こします。
症状は片側の神経に沿って現れ、痛みや水ぶくれが特徴です。合併症の一つに皮膚の症状が治ったあとにも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は70歳代台で発症することが多く、発症予防として帯状疱疹ワクチンの接種が有効とされています。
また、ワクチンには「生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)」と「組換えワクチン(シングリックス®)」の2種類があります。組換えワクチンの方が予防効果が高く(接種後5年時点で9割、接種後10年の時点で7割程度)、副反応も強めに出るのが特徴です。主な副反応は注射部位の痛み、腫れ、発赤、筋肉痛、疲労、発熱などがあります。
2025年4月から65歳を迎える方が定期接種の対象となり、60歳から64歳で重度の免疫障害がある方や、70歳以上の特定の年齢の方も経過措置で対象となります。50歳以上の方は任意接種も可能です。
肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌は鼻やのどに常在する細菌で、免疫力低下時に肺炎や敗血症といった重症感染症を引き起こします。特に高齢者や基礎疾患のある方の重症化リスクが高いため、23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)が65歳の方などを対象に2014年から定期接種化されました。
副反応は注射部位の腫れや発赤、発熱などが一般的ですが、まれにアナフィラキシー様反応やギランバレー症候群などの重い副反応も報告されています。過去5年以内に同じワクチンを接種した場合、注射部位の副反応が強く出ることがあるため、接種歴の確認が重要です。
肺炎球菌ワクチンには、免疫誘導性の高い13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)もあり、これは任意接種となっています。最近はよりカバーする型が増えた20価肺炎球菌結合型ワクチンが承認されています。
PPSV23と組み合わせて接種をすることで予防効果を高めることができます。接種のタイミングについては医師に確認してください。
インフルエンザワクチン
毎年流行するインフルエンザの重症化予防に有効とされており、毎年の季節性インフルエンザの流行前に接種したいワクチンです。特に高齢者や基礎疾患のある方や小児、妊婦などに推奨されています。
副反応は注射部位の腫れ、発熱、筋肉痛などが一般的ですが、まれにアナフィラキシーやギランバレー症候群など重篤な副反応もあります。
新型コロナワクチン
このワクチンは新型コロナウイルス感染症の重症化予防に有効で、定期接種や追加接種が行われてきました。特に高齢者は重症化するリスクが高いため、ワクチン接種が推奨されています。
高齢者や基礎疾患のある方を対象に2024年度までは自治体による定期接種が行われていましたが2025年度についての詳細については、今後の情報をご確認ください。
副反応は発熱、倦怠感、頭痛、注射部位の腫れなどが多いワクチンです。数日で軽減しますが解熱剤のアセトアミノフェンを適宜内服していただくと良いです。
子供のころに接種したワクチンのキャッチアップ接種
以下は、日本の定期接種で通常接種されるワクチンです。 日本の定期接種ワクチンは、乳幼児期から学童期にかけて計画的に接種されます。該当するワクチンには、次のようなものがあります。
- BCG
- 5種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・インフルエンザ菌b型;Hib)
- ロタウイルス
- 小児肺炎球菌
- B型肝炎
- 麻疹・風疹
- 水痘
- 日本脳炎
- HPV(ヒトパピローマウイルス) など
本来、接種すべき年齢で受けられなかったワクチンをあとから接種して免疫を補うことをキャッチアップ接種といいます。
以下のワクチンがキャッチアップワクチンとして推奨されます。
MRワクチン(麻疹・風疹混合)
MRワクチンは麻疹と風疹の2種混合の生ワクチンで、感染力や重症化リスクの高いこれらの疾患を予防します。
麻疹は、発熱や発疹をおこす疾患ですが、非常に感染力が強く、免疫を持たない人が感染する肺炎や脳炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。
風疹も発熱や発疹を起こす疾患ですが、妊娠初期の女性が感染すると胎児に白内障、心疾患、難聴などの障害を起こす先天性風疹症候群を引き起こします。
MRワクチンは定期接種対象ですので、子供のころの2回接種が推奨されているワクチンですが、成人でも子供の頃の接種を逃した方や接種歴が不明な方、妊娠希望の女性とそのパ―トナーの方は接種をおすすめします。とくに1962年から1979年生れの男性は、当時風疹の予防接種制度が男性に適応されていなかったため抗体を持っていない可能性がありますので接種をお勧めします(この年代の方への風疹抗体検査とワクチン接種代の公費助成は2025年3月で終了しました)。
HPVワクチン
HPVワクチンは、ヒトパピローマウイルス(HPV)による子宮頸癌などの発症の予防に用いられます。12歳から16歳の女子が定期接種対象です。接種機会を逃した1997年から2006年生まれ(27歳相当)の女性対象の無料のキャッチアップ接種が2025年3月まで行われました。
キャッチアップ接種期間中(2022年4月1日~2025年3月31日)に1回以上接種しているキャッチアップ接種対象者、または2025年度に定期的接種の対象から外れた方(2008年度生まれの女子)は、キャッチアップ接種期間終了後1年間(2026年3月末まで)で残りの回数(キャッチアップの方は合計で3回)を公費で接種することができます。
男性に対しても適応が広がっており、定期接種になっていませんが一部の自治体に助成制度があります。
【2025年最新版】接種が推奨されているワクチンまとめ
帯状疱疹ワクチン
2025年4月からは、65歳を迎える方が定期接種の対象。50歳以上の方は任意接種が可能。60~64歳で重度の免疫障害がある方、70歳以上の特定年齢の方も経過措置で対象となる。
肺炎球菌ワクチン
65歳以上の方が定期接種の対象。60-64歳で重度の基礎疾患がある場合は65歳未満でも医師の判断で接種が推奨される。
インフルエンザワクチン
毎年流行前の10月から12月中旬の接種を推奨。特に高齢者や基礎疾患のある方には重症化予防として重要。
MRワクチン(麻しん・風しん混合)
1歳以降に2回の接種を受けていない方、接種歴が不明な方、抗体が陰性の方、妊娠希望の女性とそのパ―トナーの方に接種を推奨。HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス)
小学校6年生~高校1年生相当の女子が定期接種の対象。男子も一部自治体で助成あり。
終わりに
本記事では、主要なワクチンの特徴や基本情報について解説しました。
正しい知識を身につけることで、安心してワクチンを選び、健康を守るための最適な選択ができるようになります。最新のワクチン事情を知り、予防接種への第一歩を踏み出しましょう。
参考資料:健康・医療 予防接種・ワクチン情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html
 この記事を監修した人
この記事を監修した人


源河 いくみ (げんか いくみ) 医師
医学博士
専門分野:感染症内科
東京ミッドタウンクリニックに勤務。 日本大学医学部卒業。医学博士。 国立国際医療センターでの感染症診療・渡航者外来での勤務を経て、現在に至る。 日本内科学会認定医・専門医。日本感染症学会専門医。 ICD(インフェクションコントロールドクター)。
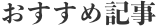 recommended
recommended
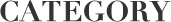 カテゴリー
カテゴリー