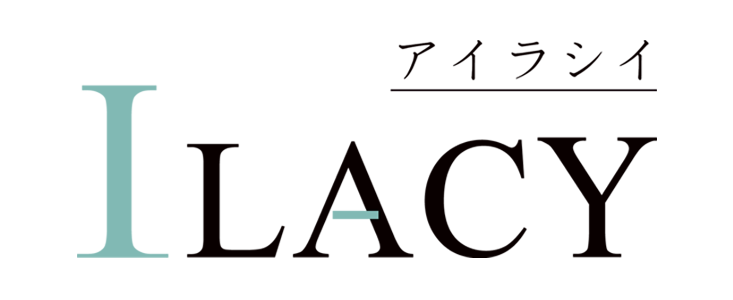【医師監修】肝臓がんに大切な「予防」「早期発見」「適切な治療」とは
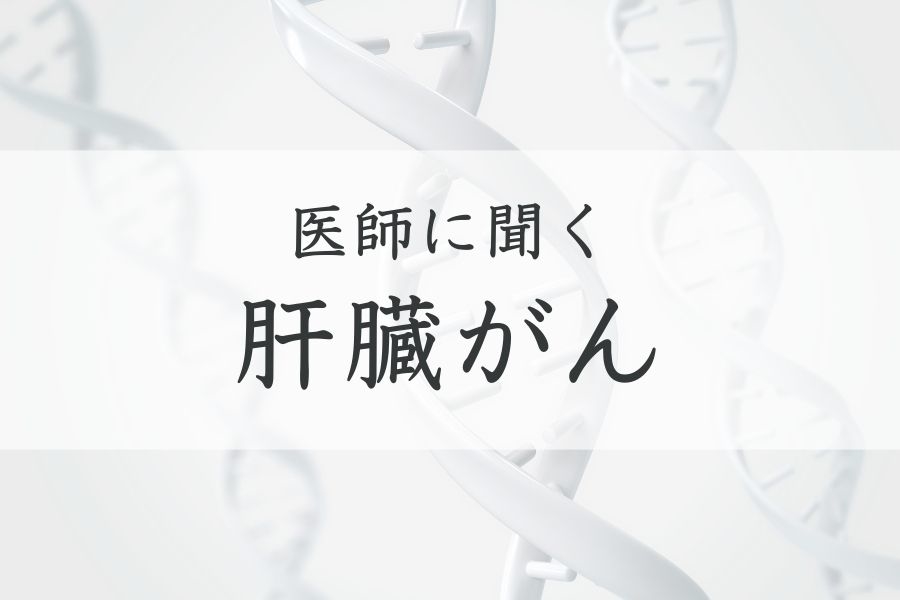

日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック
大久保 栄高(専門分野:消化器内科)
肝臓がんは「沈黙の臓器」といわれるほど、初期には症状が出にくい病気です。
疲れやすさや食欲不振など、日常的な体調不良の陰に隠れてしまい、発見が遅れやすいのが特徴です。
しかし近年は、画像診断や血液検査の進歩により、早期発見の可能性が広がってきました。治療法も多様化し、以前よりも選択肢が増えています。さらに、飲酒習慣や生活習慣病との関連が深いため、日常生活を見直すことでリスクを下げられる点も大きな特徴です。
今回は、日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニックの大久保栄高医師に、肝臓がんのリスク因子や最新の診断・治療法、そして生活の中でできる予防の工夫についてお話を伺いました。
肝臓がんに初期症状はありますか?
肝臓がんは初期にはほとんど症状がありません。だるさや食欲不振といったサインが出ることもありますが、日常的な疲労と区別がつきにくく、気づいたときには進行していることもあります。
肝臓がんの患者さんが気づきやすいサインはありますか?
代表的な症状としては「お腹が張る」「足がむくむ」「血液検査で肝臓の数値が悪い」といったものです。ただし、これらは肝臓がんそのものではなく、肝硬変などの背景疾患によって現れることが多い症状です。黄疸(顔や目が黄色くなる)も症状が進行してから現れることが多いです。
肝臓がんの見逃しやすいサインや進行してから出る症状は?
早期の肝臓がんで見逃しやすいサイン
見逃しやすいサイン(早期)として、
- 血液検査のわずかな異常(肝臓の数値が少し高い、またはほぼ正常でも注意が必要)
- 肝臓の腫瘍マーカー(AFPやPIVKA-II)が少し上がる(炎症や他の原因でも上がるので区別が難しい)
- 腹部超音波検査などの画像検査で見える小さな影(良性のしこりと区別が難しい)
- 疲れやすい、食欲低下(ただの疲れと勘違いされやすい)
などがあげられます。特に、慢性肝炎や肝硬変で定期的に通院している方は、このような小さな変化に注意が必要です。
進行した肝臓がんの症状
進行すると、腫瘍が大きくなる、腫瘍が多発する、がん細胞が血管へ入りこむ、転移をきたすなどの変化があり、下記のような症状が出現します。
- 右わき腹の痛みやしこりを触れる感じ
- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)
- お腹に水がたまる(腹水)や足のむくみ(浮腫)
- 吐血や下血(胃や食道の静脈瘤が破裂する)
- 急な体重減少や強いだるさ
- 原因不明の発熱
肝臓は非常に再生能力・予備能(余力)が高い臓器で、内部に腫瘍ができても初期には症状がまず出ません。肝臓を覆う膜、血管、あるいは胆汁を流す胆管に炎症や圧迫が及ぶと痛みや不快感として感じられることがあります。また黄疸は腫瘍が大きくなる、多発する、胆管を圧迫して流れを悪くしてしまうなどある程度進行しないと現れません。
どのようなきっかけで肝臓がんが発見されることが多いですか?
上記の症状に加えて、慢性肝炎や肝硬変を持つ方では、健康診断や定期的な検査で見つかるケースが多くあります。健診で肝臓の数値が高い、あるいは超音波検査で脂肪肝などの異常が指摘された場合には、年に1回、もしくは半年に1回といった頻度を決めて再検査を受けていただきます。リスクの高い方を拾い上げ、定期的に経過を観察していくことが何より重要です。典型的な症状や初期症状がほとんどないため、定期的に検診を受けていただくことが本当に大切だと感じています。
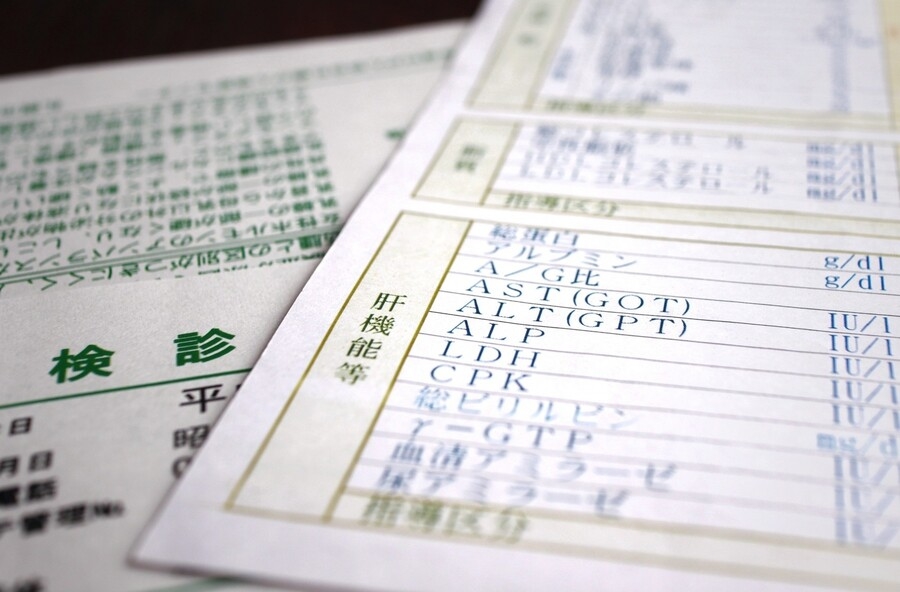
肝臓がんの主な原因や脂肪肝炎、生活習慣病に関連するリスクについて教えてください
過去にC型肝炎にかかったことがある方は要注意
肝臓がんの主な原因はC型、B型の肝炎ウイルス、アルコール、そして脂肪性肝疾患があります。日本における肝臓がんの背景は、ここ10年で大きく変化してきました。
以前はC型肝炎が最も多く、肝臓がん全体の約7割を占めていました。しかし近年、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)の登場によってC型肝炎は治療可能な病気となり、C型肝炎を原因とする肝臓がんは急速に減少しています。ただし、過去にC型肝炎にかかったことがある方では、その後も肝がんを発症するリスクが残るため注意が必要です。
生活習慣が原因となる「脂肪性肝疾患」
一方で現在は、ウイルスが原因ではない「非ウイルス性肝がん」が全体の約半数を占めるまでに増えています。特に注目されているのが「脂肪性肝疾患」です。
私たちの肝臓は、食べ物から取り込んだ脂肪や糖を処理する重要な臓器です。しかし生活習慣の乱れや飲酒、体質などの影響で、肝臓に脂肪が過剰にたまると「脂肪性肝疾患」と呼ばれる状態になります。近年では肥満や糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病と強く関連することが明らかになっており、「代謝異常関連脂肪性肝疾患(MASLD)」という新しい呼び方が使われています。
脂肪が沈着するだけの段階は「脂肪肝」とされ比較的軽い状態ですが、脂肪の蓄積に加えて炎症が起こり、肝細胞が傷ついて徐々に線維化(硬くなること)が進行すると「脂肪肝炎」となります。脂肪肝炎を放置すると、やがて肝硬変や肝臓がんに進展する可能性があります。特に脂肪肝炎を背景にした肝臓がんは、進行した状態で診断されるケースが約6割にのぼると報告されています。
また、飲酒も重要な発がんリスクです。男性でビール約2リットル(アルコール量にして80g程度)を毎日長期間飲み続けると、肝がんリスクが明確に上がることが知られています。さらに、脂肪肝のある方がアルコールを摂取すると炎症や線維化が進みやすく、肝硬変や肝がんに進む危険が高まります。特に内臓脂肪や生活習慣病を併せ持つ方では、リスクが3倍近くに増えるといわれています。
診断時に多いステージや、発見が遅れやすい理由は何ですか?
これは病態よって違いがあります。
ウイルス性肝炎を背景にした肝臓がんは、日本では比較的早期に診断される割合が多いのが特徴です。B型・C型肝炎や肝硬変などリスクが高い方には、定期的に腹部エコーや腫瘍マーカーによる検査が行われています。その結果ステージI〜II(単発、もしくは小さな多発病変)で発見される場合が多いとされています。
一方で、非ウイルス性の肝臓がんは定期的な検診を受けていない場合が多く、ステージIII〜IVの進行期で診断されやすい傾向があります。
そのため健診の場では「脂肪肝=良性」ではなく、「将来肝がんの原因となりうる病態」であることを周知する取り組みを進めています。また外来診療では消化器、肝臓内科だけでなく、糖尿病内科・循環器内科などと連携し、生活習慣病の診療の中で肝疾患リスクを拾い上げるよう日々の診療を行っています。
肝臓がん治療の基本方針はどのようなものでしょうか?また具体的な治療法に関して教えてください。

肝臓がんの治療は、がんの大きさや広がりだけでなく、前提として肝臓そのものの働き具合や体全体の健康状態を考えて決められます。というのも、肝臓がんは多くの場合、慢性肝炎や肝硬変といった病気を背景に起こるため、がんを治療すると同時に「肝臓を守ること」もとても大切になります。
治療にはいくつかの方法があります。
① 外科手術、肝移植
まず、肝臓の働きが十分であれば、手術でがんを取り除く方法が行われます。がんが一つ、または複数個に限られている場合に選択されます。さらに、病気の進み具合や肝臓の機能によっては「肝移植」が適応になることもあります。ただし、肝臓を提供してくれるドナーが必要になるため、現実には受けられる人が限られ、とてもハードルの高い治療です。
② ラジオ波焼灼療法(RFA)
手術が難しい場合には、がんを針で焼きつぶす「ラジオ波焼灼療法(RFA)」という局所治療が使われます。お腹を切らずに超音波で確認しながら腫瘍に針を刺し、その部分を高温で焼きつぶす方法です。主に3cm以下で数が限られた腫瘍に選択されます。おおむね2cm未満の腫瘍では手術と同等の効果が期待できますが、3cm前後では手術が有利とされています。
ただし、焼き残しがあると再発リスクが高まり、血管の近くや肝臓の表面を焼く場合は痛みを伴うことがあります。治療の際は局所麻酔に加えて鎮静剤、鎮痛剤を併用することが多いです。
③ 肝動脈化学塞栓療法(TACE)
がんが肝臓に複数ある場合や局所治療が難しいときには、「肝動脈化学塞栓療法(TACE)」という方法が用いられます。これは、がんに栄養を送る血管に薬やゼリー状の物質を流し込み、血流を遮断してがんを小さくする治療です。これによって腫瘍の縮小や、増殖を抑える効果が期待できます。
およそ半数の方は治療によって明らかな効果が見られ、生存期間を延ばすことにもつながります。ただし、肝臓がんは再発しやすい病気であり、TACEの後も時間が経つと新しいがんが出てきたり、残ったがんが再び大きくなることがあります。そのため、必要に応じて繰り返し行うことが一般的です。
④ 化学療法
がんが進行して肝臓の外に広がっている場合には、内服や点滴で行う抗がん剤治療が選ばれます。近年は、免疫療法と分子標的薬を組み合わせた新しい治療法が登場し、これによって生存期間がのび、生活の質を改善できるようになってきました。
従来の抗がん剤では、腫瘍を小さくできる割合(奏効率)が10%未満と低く、効果に限界がありました。しかし、免疫チェックポイント阻害薬を含む新しい薬の登場によって、現在では奏効率が30%前後まで改善しています。
一方で、肝機能が低下している方や体力が落ちている方、副作用が強く出る方では、治療の導入が難しい場合もあります。そのため一人ひとりの病状や体調に合わせて治療を選ぶことが大切です。
⑤ 粒子線治療
その他の治療として、粒子線治療があります。2022年より保険適応となった比較的新しい治療法です。がんの部分だけに強い放射線を集中させて治療する方法です。通常の放射線治療よりも、周囲の正常な臓器への影響を少なくでき、体を切ったり麻酔を使ったりせず、外来で通院しながら受けられるのが特徴です。手術が難しい場合やラジオ波焼灼療法やカテーテル治療が適さない場合、あるいは再発して他の治療法が選べない場合など特定の条件を満たした場合に選択できます。ただし、粒子線治療はすべての病院で受けられるわけではなく、限られた施設にしか設備がありません。
以上のように、肝臓がんの治療は「がんの状態」と「肝臓の働き」の両方を見極めて、その人にとって最も適した方法を選ぶのが基本方針です。
肝臓がんの治療法を選ぶときの考え方
肝臓の働きが大きく低下している場合は、どの治療法も選択できなくなることがあります。
治療にはそれぞれ利点と欠点があるため、がんの大きさや数、肝臓の状態、体力、そしてご本人の希望を総合的に考慮し、医療チームとよく相談して最適な方法を選ぶことが大切です。
肝臓がんを予防するために日常生活でできることはありますか?

これまでお話しましたように、肝臓がんの発症には生活習慣が大きく関わっています。特にアルコールの過剰摂取や肥満、糖尿病などの生活習慣病は肝臓に負担をかけ、脂肪肝や肝硬変を経て肝臓がんに進行するリスクを高めます。そこで、日常生活で意識できるポイントとしては、以下のようなものがあります。
- 飲酒量を控える:毎日のように大量の飲酒を続けることはリスクを高めます。適量を守り、休肝日を設けましょう。
- バランスの取れた食事:野菜や魚を中心にし、脂っこい食事や加工食品を控えることが肝臓への負担軽減につながります。
- 運動習慣を持つ:週に数回の有酸素運動は、肥満や糖尿病の予防に効果的です。早歩き(ブリスクウォーキング)や軽いジョギングなど、無理なく続けられる運動がおすすめです。
- 十分な睡眠と休養:肝臓は代謝や解毒を担う臓器です。しっかり休むことで回復力を保てます。
これらの工夫は特別なことではなく、日常生活に少しずつ取り入れることができます。肝臓がんだけでなく、生活習慣病全般の予防にもつながる点が大きなメリットといえます。
肝臓がんと向き合うために大切なこと
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝臓がんの初期にはほとんど症状が出ません。
だるさや食欲低下といった曖昧なサインしかなく、気づいたときには進行していた...というケースも少なくありません。だからこそ、肝臓がんは「予防」と「早期発見」が何より大切です。
そのために重要なのは、まず原因となる肝臓病を防ぎ、コントロールすることです。B型・C型肝炎の治療、脂肪肝や飲酒習慣の改善、生活習慣病の管理など、日常生活の見直しが肝臓がんのリスクを大きく下げます。
さらに、定期的な健診や画像検査・血液検査を受けることで、がんを早期のうちに発見できる可能性が高まります。早期であれば外科手術や局所治療など、複数の選択肢から最適な治療を選ぶことができます。
肝臓がんは確かに怖い病気ですが、「予防」「早期発見」「適切な治療」を組み合わせれば、結果を大きく変えることができます。ぜひ今日から、ご自身の生活を見直し、肝臓を守るための小さな一歩を踏み出していただければと思います。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人


大久保 栄高 (おおくぼ ひでたか) 医師
専門分野:消化器内科
日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック院長補佐。 日本内科学会 総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医。 日本消化器病学会 消化器病専門医。日本肝臓学会 肝臓専門医。
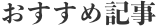 recommended
recommended
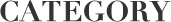 カテゴリー
カテゴリー