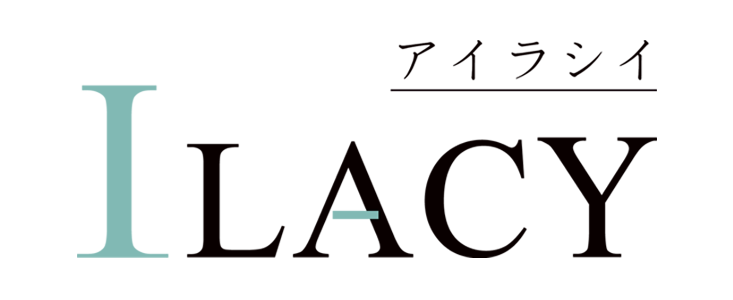【医師監修】肺がんは早期発見がカギ|リスク・症状・治療法を医師が解説
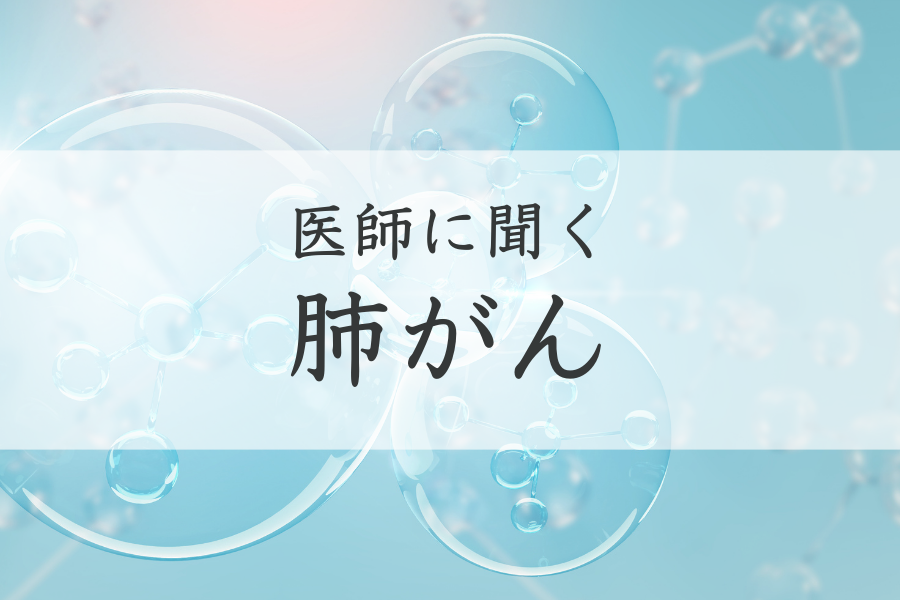
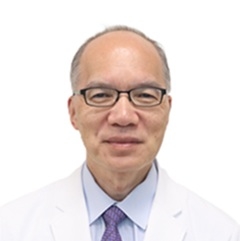
ミッドドタウンクリニックイースト
楠本 昌彦(専門分野:放射線診断科)
肺がんは、ほかのがんと同様に気づかないうちに進行してしまう病気です。初期にはほとんど症状がなく、「元気だから大丈夫」と思っている間に病気が進行し、治療の選択肢が限られてしまうこともあります。
がんの診断を受けたとき、不安や戸惑いでいっぱいになり、「これからどうすればいいのか」と悩むのは患者さんだけでなく、ご家族も同じです。
だからこそ、症状が出る前に肺がんを見つけること、そして治療や生活の中で前向きに過ごすための知識を持つことが大切です。
今回はミッドタウンクリニックイーストの楠本昌彦医師に、肺がんの初期症状やリスク要因、最新の治療法、そして日常生活での注意点まで、わかりやすくお話を伺いました。
肺がんの初期症状や、患者さんが気づきやすいサイン、見逃しやすいサイン、自覚症状にはどのようなものがありますか?
肺がんの最も大きな特徴は、がんが小さいうちはまったく症状がないことです。痛みもかゆみもなく、本人は「どこも悪くない」と感じたまま日常生活を続けられます。症状が出るのは、がんが大きくなり周囲へ病気が広がってからです。
- 咳が長く続く
- 痰に血が混じる(血痰)
- 息切れや胸痛
- 声が枯れる
- 肺炎を繰り返す
- 首や顔が腫れる
これらはすべて、がんが進行した段階(進行がん)で現れる可能性がある症状ですが、風邪や気管支炎など他の病気でも見られるため「肺がん特有」とは言えません。症状だけでは診断できず、症状を待って受診しても初期で見つかることはほぼないのが現実です。そのため、無症状のうちに定期的な検診を受け、画像で異常をとらえる早期発見が欠かせません。
肺がんの主なリスク要因について教えてください

肺がんのリスク要因は喫煙です。自分で吸うのはもちろん、家庭や職場で吸う人がいる環境(これを受動喫煙といいます)でも発症リスクが高まります。受動喫煙は、肺がんリスクを高める要因です。自らは喫煙しなくとも、職場や飲食店などで客や同僚の煙を常時吸い込む「受動喫煙環境」によって、喫煙者に近い肺がんリスクがあります。
また、喫煙者の中には肺がんを発症しない人も存在しますが、その多くはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や大動脈解離・心筋梗塞など呼吸器・循環器系の重篤な合併症になりやすいことも知られています。さらに、咽頭・膵臓・膀胱など肺以外の臓器にもがんを発症させるリスクが高くなることが知られています。
これらは肺がんとは異なる病態ですが、いずれもタバコの影響で進行する点を考えると、「吸わない・吸わせない」環境づくりが、肺がん予防のみならず、全身の健康維持に不可欠です。
電子タバコであっても、健康へ悪い影響があるとされています。
肺がん診断時に多いステージや発見が遅れやすい理由は何ですか?
がんの進行の程度は、「ステージ(病期)」として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、Ⅰ期が比較的早期で、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。Ⅳ期は、肺から離れた臓器に転移を起こしている場合を指します。
病院受診のきっかけが症状の場合、診断時はほとんどがⅢ期かⅣ期です。咳や血痰などを自覚して病院へ行く頃には、肺がんが広がり根治的治療が難しい段階に進んでいるケースが圧倒的に多く見受けられます。一方、会社検診や人間ドックでたまたま見つかった場合は比較的早期がんが多く、手術で完治を目指しやすくなります。
初期に症状がないことこそが肺がん発見を遅らせる最大の理由です。症状を待たずに受診する。つまり、無症状のうちから定期検診を続けることが早期発見への最短ルートとなります。
肺がんの治療法にはどのような選択肢がありますか?それぞれの特徴やメリット・デメリットがありましたら教えてください
肺がんは、がん細胞の性状から、大きく小細胞がん(約10%)と非小細胞がん(約90%)に分類され、治療戦略が根本的に異なります。
- 小細胞がん:進行が極めて早いため手術適応外となることが多く、抗がん剤治療が中心です。ほとんどが喫煙者です。
- 非小細胞がん:病期に応じた治療選択が可能で、Ⅰ期・Ⅱ期では手術主体とした治療で根治を目指すことが標準となっています。喫煙者だけでなく、非喫煙者にも見られます。
Ⅰ期・Ⅱ期での非小細胞肺がんの治療法
手術適応となるⅠ期・Ⅱ期での非小細胞がんでは、病巣を丸ごと摘出することで「根治(アブソリュートキュア)」を目指せるのが最大のメリットです。病変を摘出すれば5年生存率は80%前後と高く、再発リスクを最小化できます。ただし肺の一部を失うため、摘出範囲が大きいほど呼吸機能が低下し、息切れや運動時の息苦しさが生じやすくなるデメリットがあります。
Ⅲ期での非小細胞肺がんの治療法
Ⅲ期では、既に腫瘍が周囲へ広がっており、単独手術は難しいため、抗がん剤+放射線で腫瘍を縮小してから手術を行う場合があります。こうした術前化学療法は、切除可能例を増やす利点がありますが、化学療法の副作用と遅延リスク、そして手術適応が依然限られる点が課題です。
Ⅳ期での非小細胞肺がんの治療法
Ⅳ期は、肺以外の臓器に病変が及んでいるため手術や放射線治療での根治は困難です。抗がん剤治療が主体となり、症状緩和と生存期間延長が目的になります。Ⅳ期では、根治が難しい場合が多く、副作用管理と治療継続の負担が大きいことがデメリットです。ただ最近は新しい抗がん剤が開発され、Ⅲ期やⅣ期でも副作用が少なく、長期で生存できる例が増えつつあります。
どのようなきっかけで肺がんが発見されることが多いですか?また、早期に肺がんが見つかる人の特徴はありますか?(家族の気づきや、健康診断など)
肺がんはどういう時に見つかる?
肺がんの発見は「症状に気づいて受診するケース」と「検診で偶然見つかるケース」に大別されます。
症状発見では咳や血痰、息切れなど自覚症状が出た段階で受診するため、診断時にはほとんどがⅢ期・Ⅳ期の進行がんです。一方、症状のない健康な時期に定期的な検診を受けていれば、Ⅰ期・Ⅱ期の比較的早期のがんを発見しやすくなります。

胸部X線(レントゲン)検査は手軽・低コスト(約1,000円)で会社などの健康診断にも組み込まれていますが、1cm未満の小さな病変は映らないことが多い点がデメリットです。CT検査は1cm程度の小さな腫瘍も検出できる反面、費用(約1万円)と被ばく量が増え、読影にも専門性と時間が必要です。
また、CT検査では1cm程度の病変が見つかっても「がんかどうか」の判断が困難な場合があります。病変があることは分かっても、その正体が不明な状況です。ただ「すりガラス状結節」と呼ばれる病変は、病理学的には「上皮内腺癌」と診断される場合があり、これらの肺がんは進行が極めて遅く、1年経ってもほとんど変化しないことが特徴です。このような病変に対しては、1cm程度の小さなものを全て手術するわけにもいかないため、半年〜1年間隔での経過観察を選択することが多くなります。
この20年間でCT検診の普及により、こうした「すぐには治療不要だが継続的な監視が必要な病変」の発見が増えています。
早期に肺がんが見つかる人の特徴
早期に肺がんを発見できた人は、無症状でも年に一度以上必ず定期検診を受け、胸部X線(レントゲン)だけでなくCT検診も併用して小さな病変まで見逃さないことが共通しています。企業健診や人間ドックを積極的に利用して受診機会を増やし、さらに「すりガラス状結節」など経過観察を要する病変については専門医によるフォローアップを欠かさないこと。これらの習慣が、早期発見と良好な治療成績につながっています。
肺がん治療の現場で感じる課題や、今後の展望についてお聞かせください
肺がんは、非常に進行の早いものから、きわめてゆっくりと進行するものまで、様々な種類があります。診断面ではX線(レントゲン)からCTを用いた検診が普及することで、無症状でも小さながんを見つけられるようになりました。治療面でも胸腔鏡、ロボット支援手術により身体への負担を少なく病巣を摘出でき、放射線治療はより病巣に集中して放射線を照射するピンポイント照射が可能になりました。
進行がんでも治療を諦めず、がんと共存
薬物療法では分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、抗体薬物複合体など新しい薬が次々登場し、Ⅳ期のような転移のある肺がんでも、5年生存を実現する例が増えています。40年前のⅣ期肺がん5年生存率は0%に近い状態でしたが、現在は免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬の普及により、10%程度まで改善しています。しかし薬剤耐性の獲得や副作用管理、生活の質維持は依然として課題として残っています。
がん治療の目標は「治るか死ぬか」の二択を超え、がんと共存しながら社会生活を営むことが大切です。生活の質を保ちながら長く病気と共存できる時代を築くことが求められており、進行がんでも諦めず、適切な治療を受け続ける姿勢が何より大切です。
日常生活や食事で気をつけるべきポイントはありますか?
食事と肺がんの因果関係は現在まで証明されていません。塩分や糖分・欧米型食の影響は別の病気で問題になりますが、肺がんに特有の食事リスクは認められていません。
予防策として確実なのは、タバコを吸わない・吸わせないことです。電子タバコも含め、喫煙環境を避けるだけで肺がんになるリスクを大きく下げられます。
肺がんと診断されたら、まずすべきこと、病院の選び方など、患者さんやご家族が知っておくべき大切なことは?
まずは肺がん治療の実績が多い医療機関を選びましょう。外科・内科・放射線治療の専門医が横断的に連携している病院が望ましく、初回治療後の再発や転移にも柔軟に対応できます。
インターネットで情報は簡単に手に入りますが、真偽の見極めが難しく、誤情報に振り回されやすい点に注意が必要です。正しい判断には専門医から直接話を聞き、場合によってセカンドオピニオンなどを活用して、複数の情報源を照合することをおすすめします。
がんの治療は一度で完結しません。肺がんは手術後も再発や転移に備えた化学療法や放射線治療が続き、長期にわたって療法が必要なる疾患です。一度の手術で終わらない場合も珍しくありません。
患者と家族が長く医療機関と付き合う覚悟を持ち、再発や治療変更に備えた体制を整えること。そして、診断後は外科・内科・放射線科の専門家が連携する総合力のある医療機関を選び、長期的視点で医療チームと継続的に連携することがより良い結果と生活の質を守ることにつながるでしょう。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
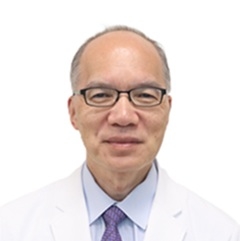

楠本 昌彦 (くすもと まさひこ) 医師
専門分野:放射線診断科
ミッドドタウンクリニックイーストに勤務。神戸大学医学部卒業。 神戸大学医学部附属病院勤務を経て、国立がん研究センター中央病院 放射線診断科科長、同病院副院長を歴任、現在に至る。国立がん研究センター 客員研究員、環境省中皮腫・肺がん審査検討会委員、日本肺癌学会特別会員。
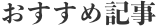 recommended
recommended
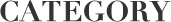 カテゴリー
カテゴリー