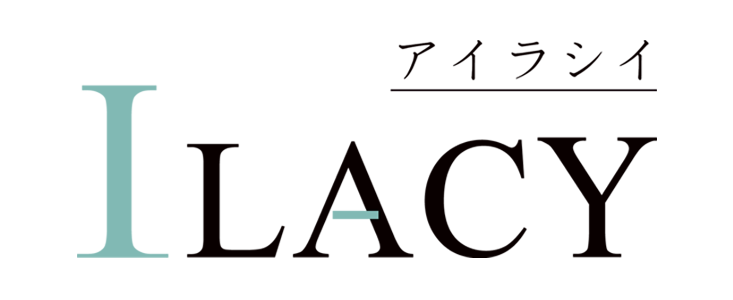親の認知症と向き合う〜介護のプロが教える予防から介護までの実践ガイド①〜

「親が認知症かもしれない」という不安を抱えたとき、どう対応すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。
介護は突然始まることも多く、知識や心構えがないままでは、家族も本人もつらい状況に陥ってしまいがちです。
今回は、介護付有料老人ホーム・トラストガーデン用賀の杜(東京都世田谷区)の介護に携わるプロの方々へのインタビューを通じて、認知症の初期症状や予防法、医療機関への相談の仕方、介護施設選びのポイント、そして家族としてできるサポートやセルフケアの知恵を詳しくご紹介します。
認知症の基礎知識から実践的な対応まで、これからの介護生活を少しでも安心して送るためのヒントをお届けします。

お話を聞いた人
【左】野田麗愛(職種:介護職員)保有資格:介護福祉士
【中央】大西まり子(職種:ケアマネージャー)保有資格:介護福祉士/介護支援専門員
【右】菅野なな(職種:生活相談員)保有資格:介護福祉士/社会福祉主事
介護付有料老人ホーム:トラストガーデン用賀の杜(東京都世田谷区)
どうなったら認知症?
認知症の初期症状にはどのようなものがあり、どのように気づくことができますか?
認知症で最も多く見られるのは、言動・行動の変化です。
普段しっかりと話を聞くことができていた方が集中できなくなったり、記憶していたことを忘れてしまったりすることが、分かりやすい症状として現れます。
こうした機能の低下は、本人自身も失われていく能力に対する不安感や焦燥感を強く感じるようになります。
家族が最も気づきやすい症状の一つが、同じ物を繰り返し購入してしまう行動です。例えば、いつものスーパーで洗剤を購入したにも関わらず、数日前に買ったことを忘れて再び同じ洗剤を購入し、結果として家の中が同じ商品のストックで溢れてしまうという状況がみられます。
| 症状の種類 | 具体的な変化 | 気づきやすいポイント |
|---|---|---|
| 記憶の問題 | 同じものを繰り返し購入 | 家に同じ商品が大量にある |
| 日常動作の変化 | 皿洗いがほとんどできていない | 洗い物の仕上がりが悪い |
| 食事に関する記憶 | 食事をしたことを忘れる | 短時間で再び食事を始める |
上記に認知症の初期症状例をまとめました。認知症の初期症状は、記憶機能の低下や日常生活動作への影響があるため、家族が日々の生活の中で気づきやすい変化としてあらわれます。
認知症予防のために
日常生活の中で、認知症予防のために特に気をつけるべきことは何ですか?
社会や誰かとつながりを持てるコミュニティに参加することです。
趣味を持っている人や積極的に社会参加をしている人は、認知症の予防効果が期待できます。
反対に、孤独や孤立状態が続くと認知症を発症するリスクが高くなってしまいます。自発的に外に出る気持ちを持つことが、認知症予防において最も大切な要素の一つです。単に外出するだけでなく、積極的に人との交流を求める意欲を維持することにもつながります。
また、食事と睡眠といった基本的な生活習慣も大切な役割を果たします。特に昼夜逆転しない規則正しい生活を送ることが重要で、太陽の光を浴びながら五感を刺激しながら日常を送るとよいでしょう。
親の認知症予防のために、子どもとして何かサポートできることはありますか?
早い段階で公的機関に相談することがおすすめです。早期に相談し、地域の集会などに参加できる環境を整えることで、認知症予防に効果的な社会参加の機会を増やせます。
何かに頼ることは、家族にとってハードルが高く感じられるかもしれません。決して悪い意味で利用するわけではないことを理解していただければ、家族も楽になります。
家族としてできることは、家族の時間を増やすことです。いつも一緒にいる家族だけでなく、家族全員での外食を企画するなど、特別な時間を作ることが効果的です。
月に1回でも構わないので、特別な時間を作ることで本人が社会参加する機会を増やすことができます。

ひょっとして認知症かな?と思ったら
親に認知症の兆候が見られたとき、どのように医療機関に相談すればよいですか?また、 どのような診断プロセスが一般的ですか?
認知症の兆候が見られた場合、まず地域包括支援センターに相談する方法があります。また、普段から通っているかかりつけ医に相談することも有効です。かかりつけのクリニックの先生から「物忘れ外来はいかがですか」という形で、"物忘れ外来"を紹介してもらうケースもあるかもしれません。
ただし、「物忘れ外来」という名称を見た瞬間に、お母様やお父様が「まだボケてないわよ」と怒り出してしまうケースがあります。本人の前では言えないようなことがあるのは、プライドや尊厳に関わる問題があるためです。
親子関係によって対応方法は変わってきます。何でも言い合えるような関係であれば、「じゃあ行くよ」と連れて行くことができますが、そうでない場合は工夫が必要です。
実際には「定期検診」という名目で連れて行くことが多いようです。「70歳になったらみんな行っているから行きましょう」といった誘導の仕方をされている方もいます。「そろそろ転んだら危ないから」など、手前の理由を作って受診につなげる工夫をしている家族も多く見られます。
本人の気持ちを尊重しながら、適切なタイミングで医療機関につなげることが大切です。
認知症と診断された直後、家族として最初に何をすべきでしょうか?
家族で協力試合の気持ちを固めつつ、公的機関に一歩踏み出して相談して施設利用や相談機関など選択肢を知ることです。介護の方法には、以下のような複数の選択肢があります。
- デイサービス利用
- ヘルパー利用
- ショートステイを利用
- 施設入所(入居)など
症状や状況にもよりますが、双方に負担がかからない環境を考えましょう。親御さん本人とって、負担やストレスにならない環境づくりと同時に家族にとっても配慮が必要です。
認知症という診断を受けた時点で、かなりの精神的負担がかかります。さらに経済的な不安や、介護をする家族が置かれている環境(仕事やキャリア、自分の家族など)についても、様々な問題が一気にのしかかってくることになります。
家族が働いている方は、付きっきり介護は困難だと思います。共倒れにならないためにも、介護保険サービスや地域のオレンジカフェなどを活用し、双方が安心して暮らせる環境づくりが重要です。
初期段階での認知症の方との接し方や、コミュニケーションのコツを教えてください。
認知症の方とのコミュニケーションは、知っているかどうかで大きく違います。一度学んでおくことで、お互いにストレスを感じることなく接することができるようになります。
大切なのは、自分の親という感覚を一旦置いて情を挟まずにコミュニケーションの工夫をすることです。認知症の方は同じ話を何回も繰り返すことがあり、人によっては何秒単位で「ご飯食べたっけ」といった同じ質問を繰り返すことがあります。
家族の場合、最初は「うん、食べたよ」と優しく答えていても「だから、さっき食べたよ」「食べたって言ったじゃない」というように、だんだん口調が強くなってしまいがちです。そうならないように、情は入れず冷静に対応することが大切です。
また、否定せず共感と傾聴を心がけることも必要ですが、家族であればあるほど難しいところでもあります。特に忙しい時間に同じことを繰り返し言われると、イライラしてしまうのは自然な反応です。
家族の理解がないと関係性が悪くなり、互いにイライラすることも。まずは、認知症が脳の病気であるということを理解しましょう。
例えば、「さっきも言ったよね」と言われても、本人からすると初めて聞いたことなのに、そう言われると「何を言っているんだろう」という気持ちになってしまいます。そのため、否定せずに淡々と根気強く伝えていきましょう。
人によっては、認知症の方が妄想や幻覚を訴える場合もあります。先程の「否定をしない」とは逆になるのですが、否定することも時には必要です。
幻視などは瞬きなどで消えることもあるため少し時間を置いてみたり、たとえばハンガーラックが人に見えているような場合は、見えているものを別の場所に移動させたりするなど工夫するとよいでしょう。対応する際は「そんなのないわけないでしょ」と強く否定すると傷つけてしまう可能性があるため、本人が見えているものを認めつつ意識を別のものに向けるのも1つの方法です。
作り話についても、認知症の進行により自分が失っているものを理解している焦りから、承認欲求が強くなり「私は大谷選手の友達なんだ」といった話をすることがあります。これは記憶障害の影響であり、正解・不正解で対応するのではなく、本人の世界観を理解しようとする姿勢が大切です。

在宅介護でできること
自宅で認知症の親を介護する際の基本的な心構えはありますか?
自宅で認知症の親を介護する際の基本的な心構えとして、「できない」ことに焦点を当てるのではなく「いまできること」に目を向けてあげることが大切です。
残された機能(できること)に焦点を当てることで、お母様やお父様の尊厳を保ちながら前向きな介護を続けることができます。認知症が進行しても、まだできることや得意なことは必ず残っているため、そうした部分を見つけて大切にしていくことが在宅介護を続けていく上での重要な心構えとなります。
認知症の進行に応じて、自宅の環境をどのように整えていけばよいですか?
認知症の初期段階では、貼り紙やチェックリストの活用が効果的です。「これはいつまで」といったメモ書きを付箋で貼ったり、重要な情報を目につく場所に表示したりします。最初はこれらの方法で気づくことができますが、徐々に景色化してしまい何が書いてあるのか認識が難しくなるという問題があるため一概にメモがよいとは言い切れません。
また、認知症の進行は予想外・想定外の状況を引き起こします。以下のような行動が見られる場合もあります。
- テーブルに飾られていた小さな花を食べてしまう
- 異食が始まり、食べるものと食べられないものの違いがわからなくなる
- ティッシュなどを口に入れてしまう
こうした状況では、様々なものをテーブルに置いておくと窒息やお腹を壊す心配があるため、安全なもので代替品を用意することが重要です。
症状がここまで進行すると、自宅での介護が難しくなる可能性があり目が離せない状況になってしまいます。危険なことや命の危険があり、目を離せない状況が続くようになった場合は在宅での介護は厳しくなります。認知症の進行段階や家族の状況に応じて、環境整備と介護体制そのものを見直すことが必要です。
物忘れや同じ質問の繰り返しといった症状にどう対応するのが良いですか?
物忘れや同じ質問の繰り返しといった症状への対応として、日記を書いてもらうことが効果的です。その日にあったことを記録する習慣をつけておくことで、記憶の整理に役立ちます。
日記を書くことは、単なる振り返りの効果だけではなく、文字を書くこと自体が脳への刺激となるため認知機能の維持にも良い影響を与えます。このような日常的な習慣を取り入れることで、認知症の進行を緩やかにし本人の生活の質を保つことが期待できます。
徘徊や妄想など、対応が難しい症状への具体的な対処法を教えてください。
徘徊への対策として、以下のような方法があります。
- GPSや携帯電話を持ってもらう
- 服の裏に名前を書く
- 靴にGPSを埋め込む、またはGPS付きの靴を使用する
- GPSや名札を下げる
ただし、GPS端末やスマートフォンを忘れてしまうケースもあるため確実性には限界があります。また、人によってケースバイケースで、夜中にスリッパで出てしまう方もいるため、普段履く靴にGPSを仕込んでも効果が限定的な場合があるため症状に合わせた対応が必要です。
また、地域によっては届け出制度を実施しているところもあります。「認知症の方で、例えばこういう人がいたら、うちの父親です」といった情報を事前に登録しておく仕組みです。行方不明者の情報を放送で流してくれる地域もあり、地域全体での見守り体制が整っているところもあります。

介護施設選びのポイント
認知症の親を施設に預ける判断はどのような場合にすべきですか?また、その際の親や家族の心理的な準備について教えてください。
認知症の親を施設に預ける判断をすべき場合として、まず命の危険が挙げられます。具体例として以下のような状況です。
- 異物を飲み込んでしまう
- すぐに外出してしまって信号などがわからないため飛び出してしまう
- いつ車にひかれてもおかしくないような状況になる
もっとも、在宅の介護はすごく家族への負担が大きいので、早めに施設入所を検討してもいいと思います。
施設に入るまでの心の準備として、実際にいろいろな施設を見学することが重要です。人それぞれに落ち着く場所はきっとあるため、複数の施設を見て回り親御さんに合った環境を見つけることで家族も安心して預けることができるようになります。
施設選びは単なる「預け先探し」ではなく、認知症の方が安心して過ごせる新しい生活の場を見つける過程として捉えることで、家族の心理的負担も軽減されるでしょう。
良い施設を選ぶポイントはどこにありますか?見学の際にチェックすべき点を教えてください。
介護施設では現在「24時間看護師がいる」といった支援はどこの施設も同じような内容になっています。そのため、施設を選ぶポイントは実際に入ってみての雰囲気や、そこで生活している人・働いているスタッフなど人の部分にあります。
施設見学の際には、設備やサービス内容だけでなくスタッフの対応や入居者の表情(活気)、施設全体の雰囲気を重点的にチェックすることが重要です。楽しい雰囲気のスタッフがいる施設では、入居者も自然と笑顔になり明るい環境で過ごすことができるでしょう。
具体的な見学時のチェックポイントとしては以下があります。
- 居室の広さや安全性
- 設備の充実度
- 食事内容
- 立地条件(部屋からの見晴らし)
施設選びでは、入居後の暮らしをイメージできるかどうかが大切で、サービスやケア体制に関する希望を詳細に施設職員に伝えて、実現可能かどうか必ず確認することが推奨されています。

公的施設入所希望で入居までの順番を待つ場合の対応はどうすればいいですか?
公的施設への入所を希望している場合、入居までの待機期間中はショートステイでつなぐことが有効な対応策となります。
特別養護老人ホーム(特養)の場合、地域によっては数百人待ちという状況もあります。一方、有料老人ホームは見学やお試し利用も可能なことが多いので、さまざまな選択肢を組み合わせてみるのがいいと思います。
施設入所後も家族としてできるサポートはありますか?
家族が関わりを持てる時間はちゃんと残してほしいと思います。
「入所したから来ない」ということではなく、最初のしばらく慣れるまでは、お越しいただいたりお電話したりといった繋がりを絶たないでほしいというのが重要なポイントです。施設入所は介護の終わりではなく、新たな形でのサポートの始まりと考えることができます。面会の際には、施設での生活で不安なことはないかを確認し親御さんの気持ちに寄り添うことが大切です。また、施設のスタッフとも良好な関係を築くことで過ごしやすい環境を整えることができます。
介護者のセルフケア
介護疲れを防ぐために気をつけるべきことは何ですか?
介護疲れを防ぐためには、仕事と家の行き来だけでなく外に出てみることが重要です。仕事と家でゆっくりするのも良いですが、ちょっと違うことをしてみることで新しい発見につながります。
介護疲れを防ぐための具体的な方法は以下の通りです。
- 外に出かけて自分の好きなことをする
- オレンジカフェや認知症の高齢者の家族会に参加する
- 同じ立場の人とのつながりを作る
特に家族のことは、一人で抱え込む人が多いため共感できる人がいることで精神面的な負担を軽減することができます。介護を全く知らない友達に話しても「分からないからどうせ話しても」という気持ちになってしまうことも。
オレンジカフェのように同じ立場の人たちとは、お互いに共感し合えて話せるという大きなメリットがあります。同じ経験を持つ人同士だからこそ理解し合える部分があり、介護の悩みや不安を安心して共有することができるのです。

仕事と介護を両立するためのアドバイスをいただけますか?
「無理をせず、完璧を求めすぎない」「人の手をかりる」ことが大切です。完璧を目指しすぎると、心身の負担が大きくなり共倒れしてしまいます。そのため、完璧でなくても良いという気持ちを持つことが重要です。
介護の便利グッズを積極的に使うことで、日常の負担を軽減できます。失禁してしまうことも出てくると考えられるため、以下のような便利グッズを使い対策を早めに講じることをおすすめします。
- リハビリパンツを早く導入する
- お布団には防水シーツを敷く
- 介護に関する知識をつける
一人で全てを抱え込まず、周囲のサポートを積極的に受け入れることが仕事と介護の両立ができるポイントです。
介護は長期戦になることが多いため、持続可能な方法を見つけることが何よりも大切です。完璧を目指さず、利用できるサービスや道具を活用しながら無理のない範囲で両立を図りましょう。
介護者が精神的・身体的に限界を感じたとき、どのような支援やサービスを頼ればよいですか?
「プロを頼る」というのが重要なポイントです。自分自身が潰れてしまう前に、適切な支援を求めることが大切です。
施設やデイサービスを含めた介護サービスの積極的な活用を、早めに考えることをおすすめします。「いざ、さあお願いします」と言っても直ぐに利用というのは現実的に難しく、申し込みから実際のサービス開始まで1ヶ月程度かかることが多いため早めに動いた方が良いです。
具体的な相談先やサービスとしては、以下があります。
- 地域包括支援センター(介護に関する無料相談窓口)
- 認知症疾患医療センターやかかりつけ医への相談
- 訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの介護保険サービス
- 福祉用具貸与・購入サービス など
地域包括支援センターでは、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーといった専門職が、福祉・保健・医療に関する相談を受け付け、必要に応じて適切なサービスや公的制度、関係機関につないでくれます。
決して一人で抱え込まず、限界を迎える前のタイミングで、これらの支援やサービスを積極的に活用しましょう。
介護のプロに頼る必要性
長年の介護経験から、家族介護者に伝えたい大切なメッセージや気づきがあれば教えてく ださい。
長年の介護経験から、家族介護者の皆さんに最も伝えたいメッセージは、「プロに頼ってほしい」ということです。
私自身の経験を振り返ると、本当にもっと早く介護施設などに頼っておけばよかったと感じています。場合によっては家族関係も悪くなってしまったりするので、そうなる前にちゃんと相談しておくことが大切です。私の場合は7人家族で、おばあちゃんを6人で見るような状況でしたが、誰かの目に届くところにいるような感じでも、徘徊で警察沙汰になることもありました。だからこそ、本当に最初に頼った方がいいと強く思います。
早めに相談することで、いい相談相手が見つかるものです。相談相手はプロでも友達でも構いません。そこからまた新しい道が見えてくることがあります。
施設の見学も早めにしておくことをおすすめします。「将来検討しています」ということで見学される方は結構たくさんいらっしゃいます。「まだ全然元気なんですけど見に来ました」という方もいるので、早めにイメージを掴んでおくことで、いざという時に慌てずに済みます。見学先でも相談ができるので、それも良い機会になると思います。
完璧を目指さず、自分らしく
一人で(家族)抱え込まずに相談すること、そして最後まで無理をしないことが一番大切です。親御さんにとっても自分にとっても、自分らしい生き方ができるように頑張りすぎないでほしいと思います。
完璧を目指さないということは本当に大事なことです。認知症になったからといって悲観的に捉える必要は全くありません。認知症の方は少なくないですし、個性だと思って楽しむぐらいの気持ちでいれば、その日その日を楽しく過ごせるのではないでしょうか。
介護は一人で背負うものではありません。周りの支援を積極的に活用しながら、無理のない範囲で続けていくことが、結果的に良い介護につながります。日々の思い出を大切にしてください。

一人で抱え込まず、相談やサービスを活用しよう
認知症の介護は、知識・準備・周囲の支えがあってこそ続けられるものです。介護施設での知識や経験にもとづくプロの介護者の言葉は、悩む家族の背中を押す実践的なヒントが詰まっていました。
「完璧を目指さず、自分らしく」。一人で抱え込まず、相談やサービスを活用しながら、本人と家族の幸せな時間を大切にしていきましょう。

トラストガーデン用賀の杜|世田谷区の介護付有料老人ホーム
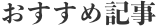 recommended
recommended
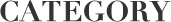 カテゴリー
カテゴリー