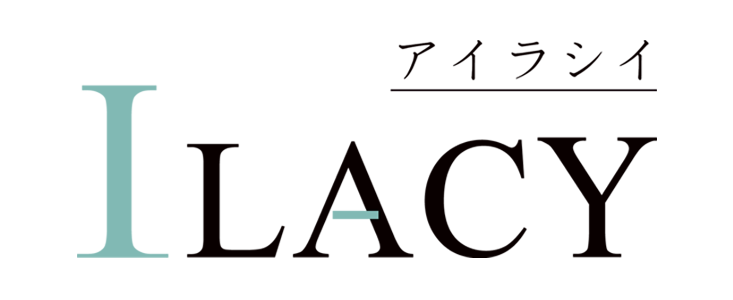親の認知症と向き合う〜介護のプロが教える予防から介護までの実践ガイド②

家族の介護は、愛情があるからこそ頑張れてしまうものです。しかし、長期にわたる介護生活の中で、気づかぬうちに心身が限界に達してしまうことも少なくありません。特に認知症介護は想定外の対応が多く、戸惑いや不安を抱えながら日々を送っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、介護付有料老人ホーム・トラストガーデン東嶺町(東京都大田区)の介護のプロの方々に認知症の基礎的な知識や介護疲れを防ぐための心得、認知症介護で避けたい対応、そして家族としてどのようなスタンスで向き合えばよいのかなどをインタビューしました。
これから介護と向き合う方にも、今まさに悩みを抱えている方にも、役立つヒントが詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

お話を聞いた人
【左】吉田友加里(職種:トラストガーデン東嶺町支配人)保有資格:介護支援専門員/介護福祉士
【右】嶋 雪枝(職種:介護職員)保有資格:介護福祉士/レクリエーション介護士
認知症に気づくきっかけ
認知症の初期症状にはどのようなものがあり、どのように気づくことができますか?
初期の段階では、普段と大きく変わった様子が見られないことが多いと思います。ただ、ご本人やご家族が「あれ? なんだかちょっとおかしいな」と感じるような小さな違和感から始まるケースが多いです。
具体的には、「物忘れが増えた」「同じことを何度も言う」「今日が何日かわからない」「季節感が薄れてくる」といった変化ですね。また、料理の手順が分からなくなったり、いつもより時間がかかるようになったりするなど、日常生活の中での小さな異変が見られることもあります。
こうした変化は、本人よりもむしろ身近な家族が会話や行動の中で気づくことが多いです。ちょっとした「いつもと違うな」という感覚を大切にしてほしいと思います。

認知症予防のポイント
日常生活の中で、認知症予防のために特に気をつけるべきことは何ですか?(食事、運動、社会活動など)
私たちが働くシニアレジデンスでも、認知症予防において大切にしている4大テーマがあります。それが、食事・運動・社会交流・睡眠です。そして、認知症予防のために日常生活で特に大切なのは、やはり「外に出て、社会とつながること」だと思います。高齢になると、どうしても体力や筋力が落ちて外出が億劫になりがちですが、家に閉じこもってしまうと、気づかないうちに人との交流が減ってしまいます。実際、そうした生活の中で、認知症が進行してしまうケースも少なくありません。
日々の生活では、「誰かと話す」「体を動かす」「きちんと食べて、しっかり眠る」といった基本を大切にしてほしいです。特に食事については、「これさえ食べれば大丈夫」という特効薬はありませんが、やはりバランスの良い食事を心がけることが健康の土台になります。そして、水分補給も見落としがちですが、高齢の方は喉の渇きを感じにくくなるため、意識して水分をとることが大切です。脱水がきっかけで体調を崩し、認知機能が一気に低下することもあるので、特に一人暮らしの方は周囲の見守りも必要だと思います。
また、普段しっかり食事を作っていた方が急に作れなくなったり、食事の回数が減ったりした場合は、認知機能の変化が隠れていることもあります。離れて暮らすご家族がいる場合は、「大丈夫」と言われても、定期的に様子を確認してあげると安心ですね。
こうした日々の小さな積み重ねが、認知症予防にはとても大切だと感じています。

親の認知症予防のために、子どもとして何かサポートできることはありますか?
親の認知症予防において、子どもができる最大のサポートは、「関わり続けること」です。定期的なコミュニケーションを通じて、日々の変化に気づきやすくなり、予防や早期対応につながります。
会いに行くことが難しい場合でも、電話やメールといった手段を活用し、こまめに連絡を取り合うことが大切です。声をかけ、様子をうかがいながら「今日は何を食べた?」「最近外に出てる?」といった何気ない会話を重ねることで、生活リズムの乱れや認知機能の変化に気づきやすくなります。
また、親が日常的にどんな人と交流しているか、どのような活動をしているかにも目を向けるとよいでしょう。もし社会とのつながりが減っていたり、以前楽しんでいた趣味に取り組まなくなったりしていれば、それもひとつのサインかもしれません。
認知症の初期対応、どうすればいい?
親に認知症の兆候が見られたとき、どのように医療機関に相談すればよいですか?また、どのような診断プロセスが一般的ですか?
親に認知症の兆候が見られた際には、まずはかかりつけ医に相談することが基本です。かかりつけ医は認知症の可能性だけでなく、一時的な脱水や体調不良によるせん妄など、他の要因の可能性も含めて判断してくれます。必要に応じて専門医や適切な医療機関を紹介してもらうのが一般的な流れです。
また、地域包括支援センターも相談窓口として機能しています。特に介護保険の申請やサービス利用に関する相談には強く、担当の相談員が症状の説明や手続きの流れなどを丁寧に教えてくれます。
診断のプロセスとしては、簡単な認知機能テストを行ったり、必要に応じてCTやMRIなどの画像検査を受けたりするケースもあります。ただし、必ずしもすべての人が専門医による詳細な検査を受けるわけではありません。かかりつけ医の判断で「認知症の症状がある」と診断されるケースもありますし、本人や家族の意向によっては、あえて本格的な診断を受けず、地域での支援を受けながら生活を続けていく選択肢もあります。
認知症と診断されたからといって、すぐに重い病気と捉える必要はありません。症状の進行度によっては、介護保険を活用しながら穏やかに暮らしていくことも十分に可能です。重要なのは、早めに気づいて、無理なく本人に合った生活のサポート体制を整えていくことです。

認知症と診断された直後、家族として最初に何をすべきでしょうか?
認知症と診断された直後、家族がまず取り組むべきことは、「病気への理解を深めること」です。認知症にはアルツハイマー型や脳血管型などいくつかのタイプがあり、それぞれ症状の現れ方や進行の仕方に違いがあります。どのような仕組みで記憶が失われていくのか、なぜ日常生活に支障が出るのかをきちんと学ぶことが、今後の接し方やサポートの仕方にも大きく影響します。
また、認知症になったからといって「すべてを忘れてしまう」というわけではありません。多くの場合、ご本人が「できること」や「思い出せること」はたくさんあります。だからこそ、診断直後から大切なのは、本人の尊厳を守り、その人らしさをできる限り尊重する姿勢です。
病気について正しく理解し、先入観や決めつけで行動するのではなく、まずは冷静に、柔軟に向き合うことが家族としての最初の一歩となります。
初期段階での認知症の方との接し方や、コミュニケーションのコツを教えてください。
初期の認知症の方と接する際には「否定しない」「怒らない」「尊重する」この3つがとても大切です。例えば、同じ話を何度も繰り返すことがあっても、「それさっきも言ったよね」と指摘するのではなく、「うんうん、そうだね」と穏やかに応じることが大切です。そうすることで、本人の不安を和らげることができ、安心感にもつながります。
ただ、こうした対応は家族側にとって負担も大きく、時には疲れてしまうこともありますので、「話題を変える」「関係のない楽しい話に切り替える」といった方法も有効です。実際、認知症の方は最近の記憶よりも昔の記憶のほうが鮮明に残っていることが多いため、過去の思い出や武勇伝などを引き出すことで、本人もいきいきと話すことができます。
また、非言語コミュニケーション、特に笑顔は非常に重要です。たとえ言葉が通じにくくなっても、「相手が笑っているか、怒っているか」は感覚として伝わります。実際に「あなたの言ってることはわからないけど、笑顔だけはわかる」といった声もよく聞かれます。マスクをしていても、目元や声のトーン、リアクションから気持ちは伝わるものです。
さらに、相手の言葉を繰り返す「オウム返し」も有効です。「はい、聞いてますよ」という意思表示になるだけでなく、言葉が聞き取りにくい方に対しても安心感を与えることができます。
家族にとってもストレスが溜まることがあるため、無理をしすぎず、自分自身のケアも忘れずに。たとえば、趣味やリフレッシュの時間を確保するなど、息抜きの場を持つことも大切です。認知症の方と心地よく向き合うためには、「ゆるやかに付き合うこと」「完璧を目指さないこと」がカギになります。
在宅介護で整えたい環境
自宅で認知症の親を介護する際の基本的な心構えはありますか?
在宅で認知症の親を介護する際に大切なのは、「自尊心を傷つけないこと」と「できる限り普段通りの生活を尊重すること」です。認知症だからといってすべてを制限したり、過剰に保護しすぎたりすると、かえって本人の不安や混乱を招くことがあります。
また、介護のために社会交流を完全に断ってしまうのではなく、外出の機会や趣味の継続など、可能な限り「その人らしい生活」を続けられるような環境を整えることも重要です。介護する側が構えすぎず、自然な関わりを保ちつつ見守ることが、結果的に本人の心の安定にもつながります。
認知症の進行に応じて自宅の環境をどのように整えていけばよいですか?
認知症の進行に合わせた住環境の整備は、本人の安全と安心を守るために非常に大切です。異食(食べられないものを誤って口にする)などのリスクがある場合は、危険な物を手の届く場所に置かない、薬の保管場所を鍵付きの引き出しや金庫にするなどの工夫が必要です。
また、「視覚的なサポート」も有効です。トイレやキッチン、薬の置き場所などをわかりやすく表示することで、本人が自立して行動しやすくなります。
ただし、認知症の方は、環境の変化に非常に敏感で、不安や混乱を引き起こしやすい傾向がありますので、環境を大きく変えすぎないことに注意してください。模様替えや家具の移動などはなるべく控え、必要な整備は段階的に行うのが理想です。住み慣れた環境の中で、必要なサポートだけをさりげなく加える、そんな"グラデーションのある整え方"が求められます。
また、本人が得意だったことや好きだったことを続けられるようにするのも効果的です。例えば、手芸が得意な方であれば、安全を確保したうえで針仕事を続けてもらうなど、「できることはできるままに保つ」ことが、本人の自信や安定感につながります。

物忘れや同じ質問の繰り返しといった症状にどう対応するのが良いですか?
物忘れや同じ質問の繰り返しは、認知症の初期段階でよく見られる症状です。対応のポイントは否定せず、穏やかに受け止めることです。同じ話を何度されても、「さっき言ったでしょ」と遮るのではなく、「うんうん、そうだね」と肯定的に受け止める姿勢が大切です。
どうしても疲れてしまうときには、話題を変えたり、昔の思い出話など本人が話しやすいテーマに誘導したりするのも有効です。認知症の方は近年の記憶よりも昔の記憶のほうが鮮明に残っていることが多いため、過去の出来事に関する会話は盛り上がりやすく、双方にとってストレスの少ないコミュニケーションになります。
徘徊や妄想など、対応が難しい症状への具体的な対処法を教えてください。
認知症が進行すると、徘徊や妄想といった対応の難しい症状が現れることがあります。こうしたケースでは、まずは「本人の安全を確保すること」が最優先です。ドアにチャイムを設置して外出に気づけるようにしたり、転落の危険がある場所には鍵をかけるなどの対策が考えられます。
ただし、過剰な施錠や自由の制限は身体拘束とみなされることがあり、介護者としての対応が問われる場面もありますので本人の意思を尊重することが重要です。最近では「徘徊」という言葉も「本人の意図を無視した見方」として使わない傾向になってきています。本人には明確な理由がある場合が多く、「子どもを迎えに行かなくては」「会社に行かなきゃいけない」といった動機が背景にあるのです。
そのため、無理に制止するのではなく、GPS端末を活用して見守ったり、「今日は日曜日ですよ」とやさしく伝えたり、「おかえりなさい」と自然に受け入れたりするなど、柔軟で思いやりのある対応が求められます。
大切なのは「本人がなぜそうしているのか」を理解しようとする姿勢。その視点があれば、たとえ一見困難な症状であっても、少しずつ穏やかに寄り添っていくことが可能になります。
施設選びのチェックポイント
認知症の親を施設に預ける判断はどのような場合にすべきですか?また、その際の親や家族の心理的な準備について教えてください。
認知症の親を施設に預けるタイミングは「一人暮らしが難しくなった」「火の不始末などの危険が増えてきた」「介護者が限界を迎えそう」などの状況などが起きたときを目安にするのもよいでしょう。
近年では、「元気なうちに入所しプロの支援を受けながら楽しく過ごす」というスタイルを選ぶ方も増えています。施設入所は"人生の終わり"ではなく、新しい生活のスタートなのです。
心理的な準備として大切なのは、罪悪感を手放すこと。ご家族が一生懸命に介護をしてきたからこそ、「施設に預ける=見捨てる」わけではありません。実際に入所後、「もっと早く入れていれば、お互いにもっと楽しい時間が過ごせた」という声も多く聞かれます。
また、施設選びの前にはぜひ見学に行ってみることをおすすめします。見学を通じて、施設の雰囲気やスタッフの対応を肌で感じることができ、抵抗感も和らぎます。体験入居を用意している施設もあるため、まずは気軽に見学してみることが大切です。

良い施設を選ぶポイントはどこにありますか?見学の際にチェックすべき点を教えてください。
施設選びで大切なのは、雰囲気と人(スタッフ・利用者)の様子です。清潔感や設備の新しさだけでなく、実際に入居者がいきいきと過ごしているか、スタッフが笑顔で対応しているかなど、"人の温度"を感じ取ることもあります。
- 利用者に笑顔があり、活気があるか
- スタッフ同士の声かけや対応が温かいか
- アクティビティ(体操・趣味活動・イベントなど)が充実しているか
- 利用者に合った環境設備が整っているか
- 匂い(不衛生さを感じさせる臭いがないか)
「静かで誰もいない」「清潔だけど無機質」な施設よりも、人の声や笑いが聞こえる活気ある場所の方が安心感があります。また、施設によってはリハビリ重視・レクリエーション重視など方針が異なるため、ご家族のニーズに合った施設を選ぶと良いでしょう。
施設入所後も家族としてできるサポートはありますか?
施設に入所したからといって、家族としての役目が終わるわけではありません。むしろ、家族の存在が本人の安心感を支える大きな柱になります。
特に大切なのは、入所後の初期段階で頻繁に会いに行くことで、新しい環境に慣れるまでの間、孤独感を和らげるためにも家族の訪問は大きな意味を持ちます。
ただし一方で、認知症の進行状況や本人の性格によっては、家族の顔を見ることで「帰りたい」という気持ちが強くなってしまうケースもあります。その場合は、施設側と相談しながら、少し距離を置いて徐々に馴染んでもらうという対応を取ることもあります。入所後も、家族ができるサポートには次のようなものがあります。
- 定期的な面会や電話、手紙などでの交流
- 一緒に外出や食事に出かける(本人の楽しみや目標になる)
- 孫や親戚とのふれあいの機会を作る
- 写真など思い出を共有して「あなたを忘れていない」ことを伝える
認知症の方は「来たことを忘れてしまう」こともありますが、"来てくれた"という感情や安心感は残ります。その安心感が日々の穏やかな生活につながっていきます。
介護者のセルフケア
介護疲れを防ぐために気をつけるべきことは何ですか?
介護は、施設に預けたから終わりというわけではなく、家族のサポートが引き続き重要になります。中でも、介護する側の心身の健康を守る「セルフケア」は非常に大切です。
まず意識しておきたいのは、「自分の時間をしっかり確保すること」。好きなことをする時間、たとえば趣味や友人との時間、推し活やお酒を楽しむ時間などが奪われてしまうと、介護に対する気力も失われてしまいます。介護を担う人がリフレッシュできる時間を持つことは、決して贅沢ではありません。
また、地域の家族会や「オレンジカフェ」のような集まりに参加するのも有効です。そこでは同じ悩みを持つ家族と話をすることができ、自分の置かれた状況を共有したり、他の家庭の工夫を知ったりすることで、気持ちが軽くなることもあります。誰かと悩みを共有する場を持つことは、心の支えになるのです。
仕事と介護を両立するためのアドバイスをいただけますか?
仕事と介護の両立は多くの人にとって現実的な課題ですが、無理に一人で抱え込まないことが最大のポイントです。
介護には多様なサービスがあります。「月・水・金はデイサービス」や「火・木・は訪問介護」といったように、1週間のスケジュールをうまく組み立てていくことで、在宅介護でも無理なく続けていける家庭もあります。必要に応じて施設利用を選ぶことも、前向きな選択肢の一つです。
また、家族間で介護の役割分担について話し合うことも大切です。「自分しかやる人がいない」と思い込みすぎないこと。柔軟な考え方と周囲の協力を得ながら、働くことと介護の両立を目指すことが、長続きの秘訣です。
介護者が精神的・身体的に限界を感じたとき、どのような支援やサービスを頼ればよいですか?
介護者が心身ともに限界を感じたときは、「プロに頼る」ことをためらわないでいただきたいです。介護保険を利用している場合には、必ず担当のケアマネージャーがついています。まずはそのケアマネージャーに相談するのが第一歩です。
施設入居中の場合は、その施設内にも担当のケアマネージャーや生活相談員がいるため、そこに相談することも可能です。もしまだ何のサービスも使っていない場合でも、「地域包括支援センター」という公的な相談窓口に連絡することで、必要な支援につながることができます。
実際に、介護のストレスで精神的に追い詰められてしまい、大声で叫んでしまうような状態になっていた方もいました。そうしたケースでは、ご近所の方から施設に相談が入り、支援へとつながった例もあります。介護は孤立して行うものではありません。支援を必要としていることを周囲に伝え、専門機関とつながることが、何よりも重要です。

尊厳を大切にする介護
長年の介護経験から、家族介護者に伝えたい大切なメッセージや気づきがあれば教えてください。
介護を長く続けていく上で最も大切なのは、「一人で抱え込まないこと」です。自分だけでなんとかしようと無理をしてしまうと、心身ともに追い込まれ、介護そのものが辛くなってしまいます。
「頑張りすぎないで」という言葉は、介護施設のCMなどでもよく使われていますが、それだけ多くの人が無理をしてしまっているという現実があります。家族の介護に一生懸命になるのは素晴らしいことですが、自分の生活や心のゆとりを壊してまで頑張る必要はありません。
介護保険のサービスは、そうした家族を支えるために整備されてきた制度です。訪問介護やデイサービス、ショートステイなどをうまく活用することで、自分自身の気持ちを立て直す時間が生まれ、結果として被介護者との関係も良好に保つことができます。「こうしなければならない」と思い詰めず、柔軟にサービスを取り入れていくことが、長く穏やかな介護を続けるコツです。
認知症介護において、よくある間違いや避けるべき対応はありますか?
認知症介護では、「怒らないこと」が基本です。介護する側が複数人いて、一度にあれこれ指示を出してしまうと、本人が混乱してパニックを起こすことがありますので、焦って解決しようとせず、ゆっくりと、一人が声をかけて対応することが大切です。
また、家族の中には認知症の診断を避けるケースもあります。認知症と告げられることはショックですが、必要に応じて専門医の判断を仰ぎ、正しく状況を把握することが重要です。とはいえ、医療的な診断にこだわりすぎず、本人の気持ちを尊重する姿勢も同時に求められます。現場では、認知症と診断されてもそのことを必要以上に本人に伝えず、あえて話をそらす対応をすることもあります。
さらに、認知症だからといって、できることをすべて取り上げてしまうのは避けたいところです。本人がこれまで担ってきた役割や習慣を、できる限り続けられるようにサポートすることで、生活の質が大きく向上します。具体的には、家事の一部を任せる、お茶を入れてもらうなど、日常の中で役割を持つことで本人の意欲や自尊心を保つことができます。
加えて、女性の利用者にとっては「身だしなみ」も重要です。明るい色の服を着る、お化粧をするなど、外見を整えることで気分が上がるという方は少なくありません。こうした「美」に関するケアも、精神的な安定や生きがいにつながるため、見逃せない要素です。
認知症になったからといって、人生が終わるわけではありません。本人の尊厳を保ちながら、可能な限りその人らしい生活を支える視点を大切にしたいものです。

頼れるものはフル活用を
介護を続けていくには、何よりも「ひとりで抱え込まないこと」が大切です。介護保険サービスや地域のサポート、身近な人との分担をうまく活用することで、心に余裕が生まれ、より良い関係を築くことができます。
また、認知症介護では怒らず、焦らず、本人の尊厳を大切にすることが重要です。小さな気づきと工夫が、介護の質を大きく変えてくれるはずです。

トラストガーデン東嶺町|大田区の介護付有料老人ホーム
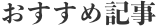 recommended
recommended
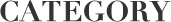 カテゴリー
カテゴリー