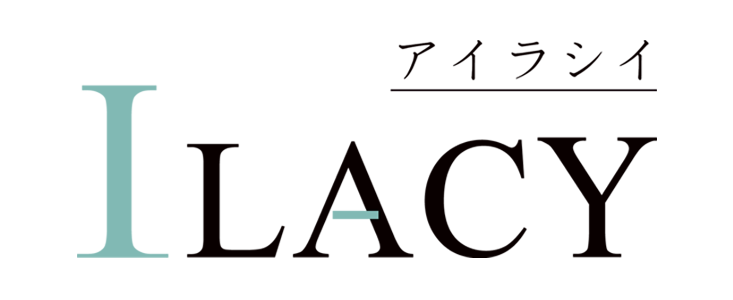お腹が張る・パンパンになる原因はガスだまり?ガス抜き対策になる食べ物と運動とは(2025年更新版)

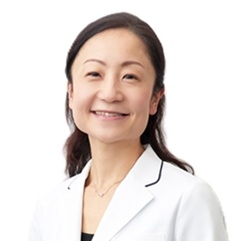
東京ミッドタウンクリニック(東京・六本木) / イーク表参道
古川 真依子(専門分野:消化器内科・内科)
座ったときにウエストがきつい、食べてすぐおなかが張って苦しい、便は出ているのに残便感がある――長引く胃腸の症状の原因として考えられるのが、おなかに溜まる「ガス」です。不快な思いをしながらも、「便秘で病院にかかるのは恥ずかしい」「症状を説明しにくい」と、我慢して過ごしている方も多いのではないでしょうか。
おなかのガスは、消化しきれなかったり、分解できなかったりした老廃物が腐敗して発生するもの。放置していると肌荒れやむくみなどを引き起こし、美容や健康に大きな影響を与えることになりかねません。
今回は、女性に多い「ガス溜まり」の原因と対策について、消化器内科の医師である古川真依子先生に教えていただきました。
※本記事は、2019年1月8日公開版を更新したものです
そもそも、女性は便秘になりやすい
――おなかが張って苦しい、おなかがぽっこり出ていて気になる、という女性は多いと思います。皆さん、どのようなきっかけで受診されるのでしょう。
女性の場合、ほとんどが便秘ですね。排便の回数や量は個人差が大きく、「何日以上出ないと便秘」というような明確な定義はありません。「十分に出し切った感覚がなく、いつも残便感があってつらい」「おなかが張って苦しい」といった自覚症状が受診の目安です。
あとは、「食欲がなくなった」「食べると吐き気がする」「胃がむかつく」といった症状を訴える方も多いですね。便が溜まりすぎると、便とガスで胃や腸が圧迫されて、こうした症状が出ます。
――なぜ、女性は便秘になりやすいのでしょう。
そもそも、男性と女性では体の作りが違います。女性の骨盤は男性に比べて広く、腸が骨盤の中に入り込んでたるみやすいので、便が溜まってしまうんです。内臓脂肪がつきやすい上、腹筋が弱いので、便を送り出す力が弱いというのもありますね。
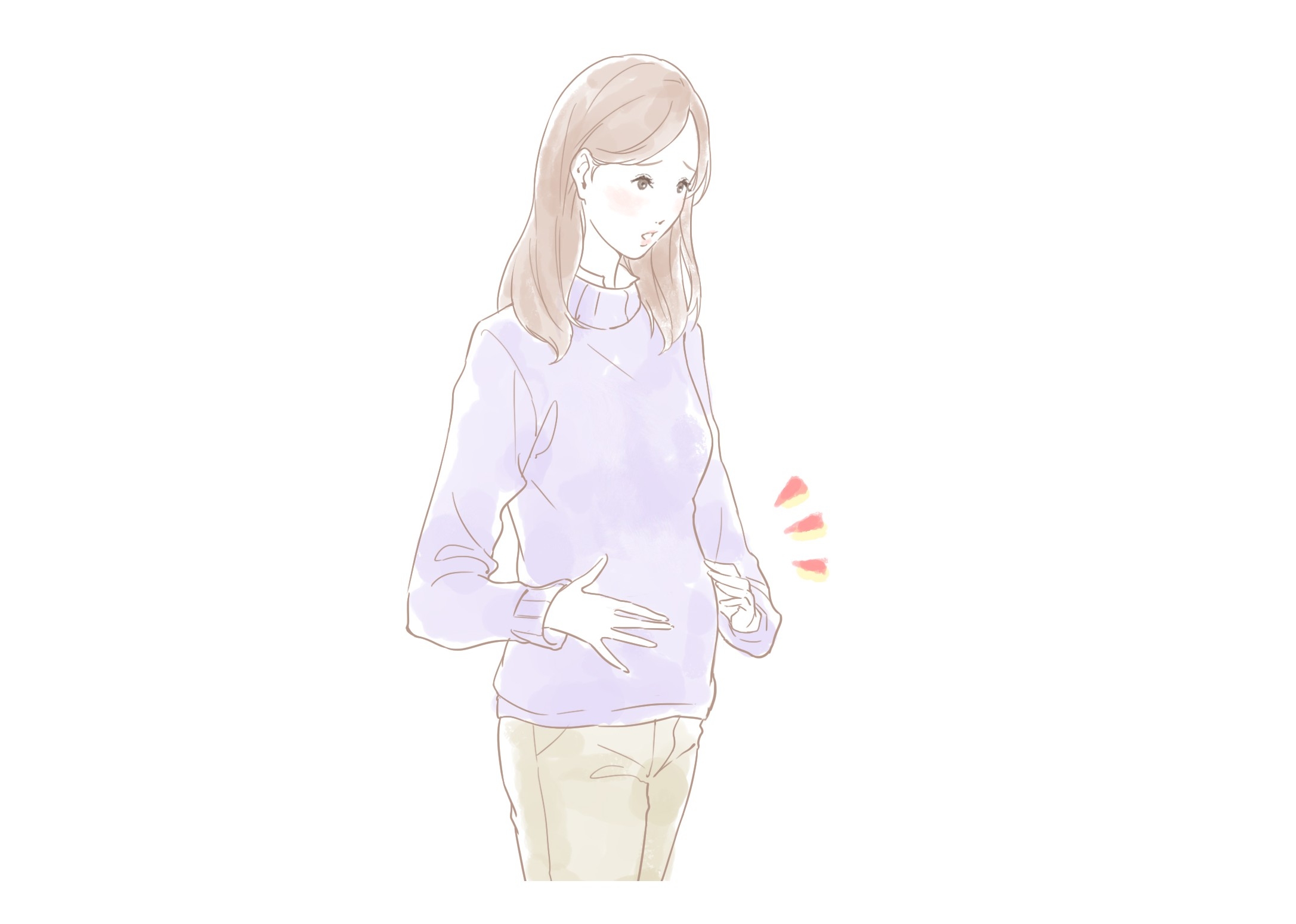
おなかがつらい、苦しいと感じたら受診のサイン
――ガスが溜まるメカニズムについて教えてください。
食べ物の通り道である胃や腸のガスは、食事をすると必ず発生し、呼吸やおならとともに体外に排出されます。ところが、何らかの理由でおなかの動きが鈍くなると、排出が滞って体内のガスの量が増え、「おなかが張る」「おなかが苦しい」といった、自覚症状を伴うガス溜まりにつながってしまいます。
おなかの動きが悪くなる原因としては、食事の内容や摂取した水分の量、風邪などのウイルスやストレス、ホルモンバランスの乱れなどが考えられますね。原因はひとつではなく、複合的に絡み合っていることがほとんどです。
――便秘で受診するのは恥ずかしい、と躊躇してしまう方も多そうですが...。
ガスは老廃物から出た、体外に排出されなければならないものです。溜まったままにしておくと、常におなかが苦しいばかりか、肌荒れやむくみなどを引き起こし、美容にも大きな影響を与えます。また、ガスをきっかけに炎症が起き、消化管の病気につながる可能性もあります。なので、「つらい」「苦しい」と感じたら、早めに医療機関に行くことをおすすめします。
――医療機関では、どのような治療をするのでしょう。
まず、食事の内容や排便のリズム、いつごろから症状を自覚しているかなどについて伺った後、患者さんのおなかをさわったり、必要であればレントゲンを撮ったりして、患者さんが訴えるおなかの症状がガスによるものなのか、ほかの病気によるものなのかを見極めます。
便秘やそれによるガスが原因なら、まずは下剤を処方するのが一般的でしょう。私の場合、強い薬で一時的な排便を促すよりも、自然に近い排便習慣を取り戻すことを目的として、漢方を含めたさまざまなお薬から患者さんの体質や生活習慣に合った物を選んで処方しています。患者さんに状況を伺いながら、処方する量や薬の種類を調整していくことも多いですね。
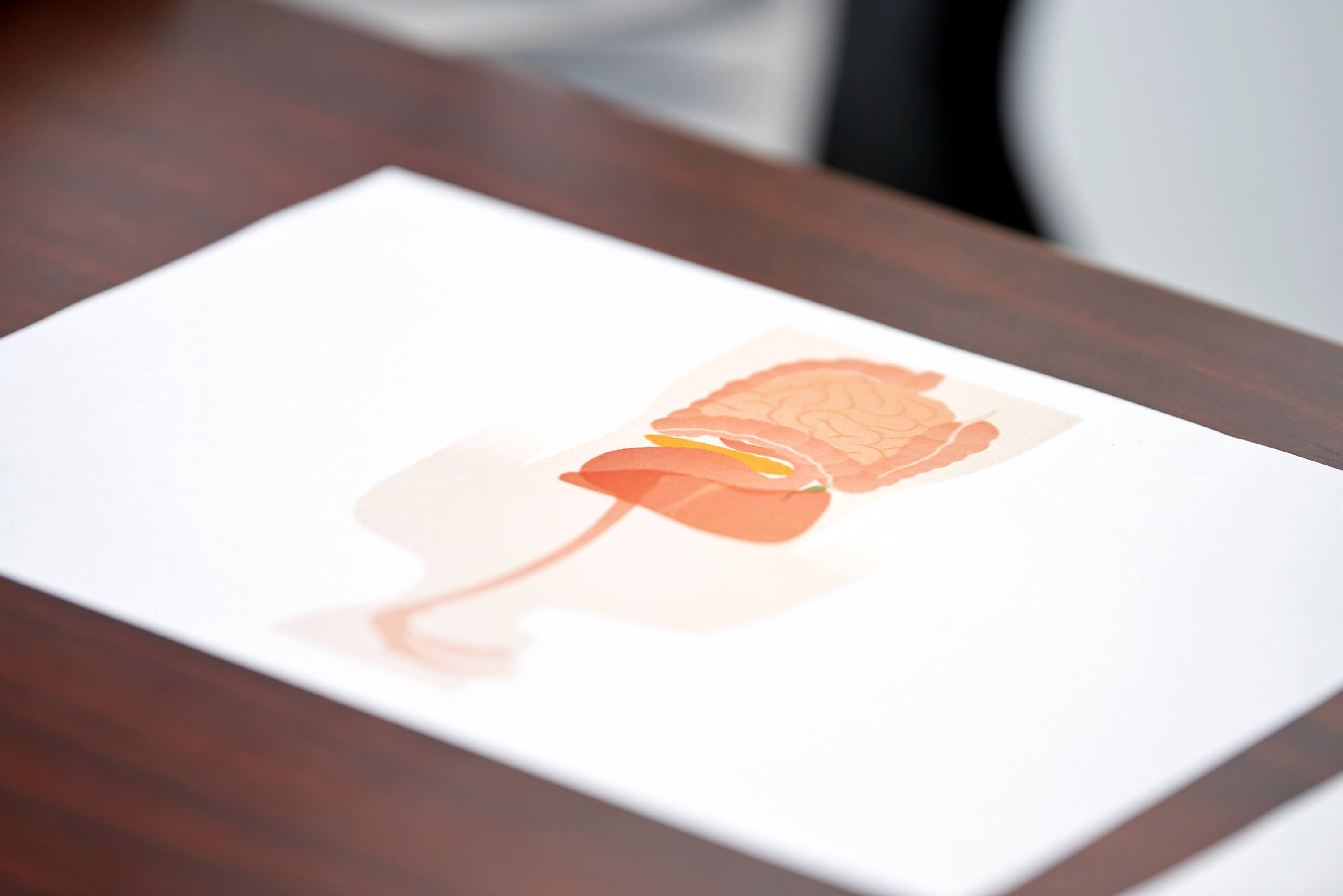
ガス溜まり予防のポイントは「食事と運動」
――ガス溜まりを防ぐには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか。
ガス溜まりを予防するには「いい便を作ってしっかり出す」ことが重要ですから、バランスの良い食事を3食とっていただきたいですね。ダイエットのために炭水化物を抜く方が増えていますが、おなかのためにはおすすめできません。
どうしても炭水化物を抜きたい場合は、夜だけ抜くなどしましょう。消化を良くするため、よく噛んで食べることを心掛けるといいと思います。就寝前2時間くらいは何も食べずに胃腸を休ませ、起きたらすぐに水分を取って胃腸を起こすことも効果的ですよ。あとは、適度な運動ですね。
――忙しい人でも、自宅で簡単にできる運動はありますか。
まずは、排便をするために必要な筋力である腹筋を鍛えましょう。腹筋がつくと、腸のたるみを引き締め、代謝を良くして腸を動かす効果も期待できます。本格的な筋トレまでいかなくても、寝転がって脚を伸ばし、下っ腹を意識してちょっと頭を上げるだけでも構いません。テレビを見ながらでもできますよ。
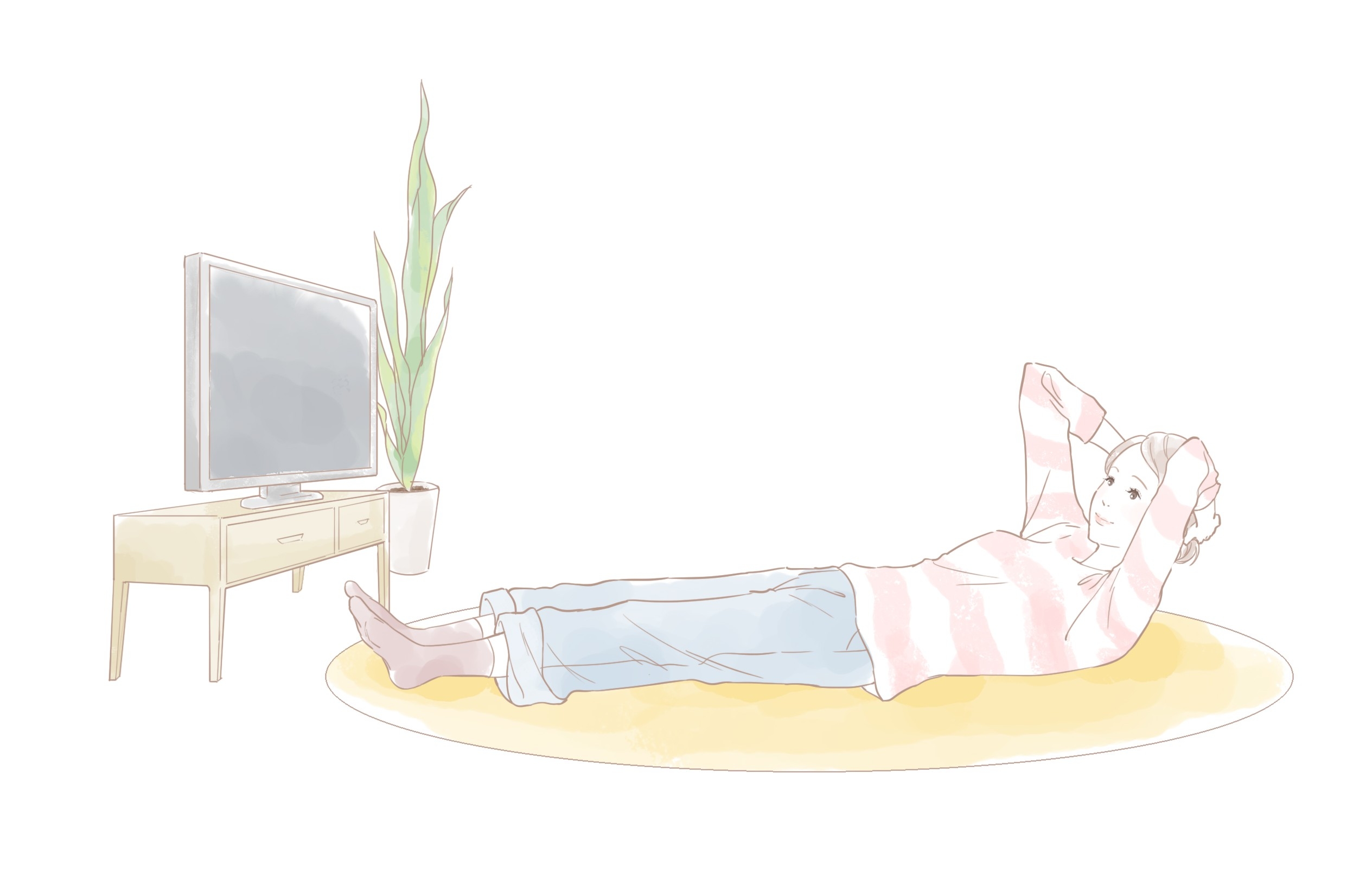
――それくらいなら、毎日継続できそうですね。
健康的で美しい毎日を送るには、しっかり便を出すことが大切です。胃腸がすっきりすれば、仕事や家事、育児など、やるべきことに対する集中力も高まるでしょう。ぜひ、食事と運動に気を配り、ガス溜まりを未然に防いでほしいと思います。 おなかがつらい・苦しいは体からのサインです。症状が悪化しないうちに、できるだけ早く専門の医療機関を受診するようにしましょう。
月経前や月経中にお腹が張る理由
ここからは、古川先生のお話に関連して、月経の時期に起こるお腹の張りに関する情報をお届けしていきます。
古川先生のお話によると、そもそも女性は男性と比べて便秘やガス溜まりが起こりやすい傾向にあることがわかりました。実際にこうしたお悩みを抱える女性のなかには、月経前や月経中にお腹の張りを特に感じる方が多いのではないでしょうか。
月経前にお腹が張る主な理由は、プロゲステロン(黄体ホルモン)という女性ホルモンの分泌量が変化し、子宮や腸の動きに影響を与えるためです。プロゲステロンには、体内に栄養や水分を蓄え、妊娠しやすい状態を維持するはたらきがあります。その影響で子宮が厚くなったり、腸がむくんだりして腸の動きが低下すると、便秘やガス溜まりにつながるのです。
月経前や月経中のお腹の張りを予防・軽減する具体的な方法
月経前や月経中のつらいお腹の張りですが、「我慢するしかない......」というものではありません。
ここでは、お腹の張りを予防・軽減するための7つの方法を紹介します。
食事を調整する
月経前や月経中は、体内の塩分量や腸内環境を整える食事を意識すると、お腹の張りを和らげる効果が期待できます。
たとえば、バナナやほうれん草などのカリウムを多く含む食品は、体内の余分な塩分の排出を促し、腸のむくみ緩和を助けてくれます。
また、海藻やキノコなどといった食物繊維の多い食品を積極的に摂り、腸内環境を整えることも効果的です。さらに納豆や味噌などの発酵食品と一緒に摂取すれば、腸内の善玉菌が増え、便秘の解消につながります。
なお、症状を悪化させないために、タンパク質を摂り過ぎないことも重要です。肉や魚などのタンパク質は健康を維持するうえで重要な栄養素ですが、摂り過ぎると悪玉菌のエサとなり、お腹の張りやガスが溜まる原因となる可能性があります。
このほか、ブロッコリーやカリフラワーなど、アブラナ科の野菜はガスの発生源になるといわれているので、ガスがだまりの自覚があるときは摂取を控えたいところです。
食事の調整は、お腹の張りを解消する根本的な治療とはいえないものの、不快感を軽減するために試すことをおすすめします。
炭酸飲料を避ける
お腹の張りを予防・軽減するためには、炭酸飲料を控えることも重要です。
月経前や月経中はホルモンバランスが乱れがちなため、通常よりも腸の機能が低下することが予想されます。このような状態で炭酸飲料を飲むと、炭酸ガスが胃腸にたまってしまうことがあります。 月経の時期は、炭酸飲料を控えた水分補給を心がけましょう。
カフェインやアルコールを避ける
月経前や月経中は、炭酸飲料だけでなく、カフェインやアルコールを含む飲み物を控えるのもいいでしょう。
カフェインやアルコールには利尿作用があるため、飲み過ぎると体内の水分が過剰に排出されてしまい、便秘の原因につながります。
症状を悪化させないためにも、月経の時期はカフェインを含むコーヒーやお茶、またアルコール飲料を控えるよう意識したいところです。
喫煙を避ける
タバコには、ニコチンが含まれており、血管を収縮させ血行不良を引き起こすリスクがあります。血流が滞るとむくみが悪化するだけでなく、ホルモンバランスが崩れて便通の乱れにもつながります。
ニコチン摂取で一時的にお通じがよくなることもありますが、たばこの吸い過ぎでニコチンを多量に摂取すると、血流が滞るだけでなく腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)も低下するため、便秘になるおそれがあります。
普段からタバコの量を減らすことを心がけ、不調を予防するのが理想的です。
睡眠をしっかりとる
月経中のお腹の張りを緩和するためには、十分な睡眠をとることも欠かせません。
睡眠不足は、自律神経の乱れから腸の機能を低下させるおそれがあります。
腸のはたらきは睡眠中に活発になるため、睡眠不足はお腹の張りや便秘を引き起こす原因となりえるのです。
就寝前にリラックスすることが良質な睡眠につながり、さらに腸の活動を助けることにもつながります。
適度な運動やマッサージをする
適度な運動やマッサージをすることも、お腹の張りを軽減するために効果的です。
軽いストレッチやウォーキングは、血行を促進して腸の動きを活性化します。また、お腹周りを揉みほぐして腸に刺激を与えると、便通の改善にもつながります。運動を取り入れるときは体に負荷をかけすぎず、無理のない範囲で行いましょう。
医療機関を受診する
ここまで紹介した方法を試してみたものの、お腹の張りが改善しない場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
月経の時期に症状がみられる場合には、婦人科の受診をご検討ください。
婦人科では、症状を緩和するために、薬や漢方薬が処方されます。また、むくみの治療として体内に溜まりすぎている水分を解消する目的で、利尿剤を処方してもらえる場合もあります。
なお、普段からガスが溜まってお腹が張る場合や便秘で苦しい場合は、内科や消化器内科の受診を検討したほうがよいかもしれません。
「いつものことだから......」と我慢せずに、症状がつらいときは医療の力を借りてみてはいかがでしょうか。
お腹が張るときに隠れている可能性がある病気
月経の時期になると毎回のようにお腹が張る、また月経にかかわらずお腹がパンパンに張るといった場合は、なんらかの病気が隠れているサインかもしれません。
以下では、お腹の張りを引き起こす可能性がある代表的な病気を紹介します。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、大腸や小腸に異常が見つからないにもかかわらず、お腹に張りや痛みを引き起こす病気です。
発症の主な原因は、ストレスや不規則な生活により、腸の機能に異常が起きることが挙げられます。
男性よりも女性に発症する人が多く、お腹の張りや腹痛、便秘や下痢などを繰り返します。
大腸がん
大腸がんは、結腸や直腸を含む大腸内の粘膜に発生するがんです。
早期の場合は症状がほとんどみられませんが、進行するとお腹が張る症状や、便秘と下痢を繰り返す便通異常が起きることがあります。
大腸がんを発症には生活習慣が関係していると考えられており、飲酒や喫煙の習慣がある方や、加工肉や牛肉・豚肉をよく食べる方に発症するリスクが高いとされています。
なお、大腸がんは早期に発見できれば治せる可能性が高い病気です。お腹の張りが続く場合や気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診して、治療を開始することが重要です。
更年期障害
更年期障害とは、加齢に伴い女性ホルモンが低下し、心身にさまざまな症状をきたす病気です。
更年期障害の代表的な症状としてホットフラッシュや疲労感、また肩こりや腰痛が挙げられ、なかにはお腹の張りを引き起こすこともあります。
そもそも"更年期"とは、閉経を中心とした前後の10年間程度の期間のことです。一般的には45~55歳ごろが対象年齢とされますが、早い場合には40代未満で閉経となり、更年期症状が出るケースもあります。
更年期の期間は個人差が大きいため、お腹の張りや気になる症状が表れた際は、医師への相談をおすすめします。
月経困難症
月経困難症とは、月経に伴う不快な症状のことで、主に下腹痛や腰痛、頭痛、またお腹の張りを引き起こします。
身近な症状のため、医療機関の受診を避けてしまいがちですが、子宮筋腫や子宮内膜症が関係していることも少なくありません。
月経困難症は、医療機関での治療により症状の改善が期待できます。不快な症状に1人で悩まず、医師に相談することが大切です。
子宮腺筋症
子宮腺筋症は、子宮内膜に似た組織が子宮筋層内にでき、増殖する病気です。
子宮内膜は子宮の一番内側を覆っている組織ですが、それがなんらかの理由で子宮の筋肉の中に入り込んでしまうと考えられています。
強い月経痛や過多月経を引き起こす要因となり、
病変によって筋肉組織が通常よりも厚くなると、それに伴って子宮全体も膨らみます。大きくなった子宮に圧迫されてお腹の張りが引き起こされるケースもあるので、ただのお腹の張りと侮らず、婦人科で検査を受けることをおすすめします。
子宮筋腫
子宮筋腫とは、子宮の筋肉にできる良性の腫瘍のことで、30歳以上の女性の3人に1人にみとめられます。子宮筋腫ができる明確な原因はわかっていませんが、悪性になる確率は少ないといわれています。
代表的な症状としては、過多月経が挙げられ、貧血を起こす場合もあるため注意が必要です。進行して筋腫が大きくなると、お腹に張りを生じることも懸念されます。
筋腫は女性ホルモンによって大きくなるため、閉経後は縮小していきますが、気になる症状がある場合は早めの受診を心がけましょう。
お腹が張ってつらいときは、我慢せずに医療機関を受診しよう!
今回は、古川真依子先生にお腹のガス溜まり予防をお伺いしたのち、月経の時期や病気などが原因のお腹の張りについてお伝えしました。
月経前や月経中は、女性ホルモンの分泌量が変化することにより、子宮や腸の動きに影響を与えるため、お腹の張りやさまざまな不調が起きやすくなります。
食事や運動を調整すれば、一時的に症状を緩和できるかもしれません。
しかし、お腹の張りが続く場合には、病気が原因の可能性も考えられます。気になる症状が表れた際には、自己判断はせずに医療機関を受診することをおすすめします。
 この記事を監修した人
この記事を監修した人
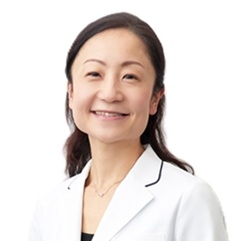

古川 真依子 (ふるかわ まいこ) 医師
医学博士/日本内科学会 総合内科専門医
専門分野:消化器内科・内科
日本消化器病学会 消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化管学会 胃腸科専門医、日本ヘリコバクター学会 ピロリ菌感染症認定医、日本カプセル内視鏡学会 カプセル内視鏡認定医、健診ドック専門医、日本医師会認定産業医。 2003年東京女子医科大学卒業。東京女子医科大学附属青山病院消化器内科で医療錬士として関連病院等にて診療にあたり、2008年帰局後は助手として指導にも尽力。2013年より東京ミッドタウンクリニック勤務。胃がん・大腸がん・腫瘍など消化器系の疾患だけでなく、便秘や産後の痔など女性ならではの悩みにも詳しい。
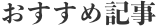 recommended
recommended
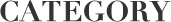 カテゴリー
カテゴリー